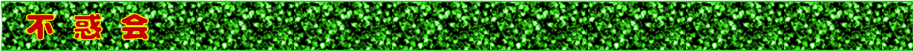
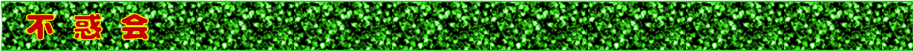
広島被爆直後の救援活動
危機管理の視点から

喜田 邦彦
6 区 隊
職種:普通科
今年の1月3日、中国新聞(本社広島)が一面トップで、「(広島)被爆直後の救援命令書を防衛研究所が保管している」と報道した。 「極秘」の印がある『船防作命』と標記された陸軍船舶司令部の50頁の史料である。(注 上級部隊の作戦命令書は、文書規定で極秘の区分になる) この報道は何を意味するか。 実は今まで、被爆直後の救急活動〜復旧活動を、①誰が主導し、②何の根拠に基づいて、③どんな活動を、④どうやって行ったか、について確たる証拠史料はなかった。 したがって、広島原爆資料館の展示をみても、救援関係のスペースと展示は極めて少ない。 70周年を迎えた今年の記念式典でも、それにあたった人達への感謝どころか、言及さえなされなかった。 残存放射能のある生地獄の中で、自らの命を顧みることなく、救援活動で1万5千余の人命を救い出しただけでなく、事後の復旧活動に筋道をつけたのが、陸軍船舶部隊・同司令部・佐伯文朗中将であることが、この救援命令書でようやく証明され、報道されたのである。 広島被爆直後の救援等については、反核・平和運動、反軍・戦前体制の否定、各種団体の思惑等から、本格的検証は行われてないようだ。 地元ではタブー視されているのかもしれない。 思考停止の針を戻し、上述の①〜⑤について、危機管理の観点から迫ってみたい。 「後知恵の弊害」は免れなことは承知の上である。 1 「世界一の防災都市」の状況 1945年8月6日8時15分、広島市は都市防災対策として空き地作りの『第6次建物強制疎開作業』を進めていた。 ところが空襲警報等のため、8時からの作業開始は遅れ、陸軍の将兵、各地域・職場からの勤労奉仕、国民義勇隊、中学や高等女子学校の動員学徒らが集合する状況で、原子爆弾が炸裂した。 空襲警報は、原爆投下の1時間前に出されたた。 気象観測用の B29が広島市に侵入し、それが播磨灘方向に離脱した7時31分に解除された。 広島県・市は、人知を尽くして防空計画を練り、防災準備・訓練を行っていた。 だがそれらは、被爆段階で効果を発揮することはなかった。 まず、陸軍の全般防空はどうだったか。 終戦直前、本土防空のため、全国に百数十の飛行場を展開し、約2300機の戦闘機を配備していた。 レーダー開発に遅れをとったとはいえ、戦闘機と高射砲の連携で、20年1月には来襲したB29の5・7 %に損害を与え、2月だけで39機を撃墜していた。 ところが3月に入ると、米軍は「高高度精密照準爆撃」の方針を、大都市・航空機工場への「夜間低高度焼夷攻撃」に転換した。 結果的に陸軍は、3月24日から5月19日の間、B29延べ1433機に対し、 1・3%の損害しか与えられなかった。 6月中旬になると米軍は、66の中小都市にまで爆撃範囲を拡大したため、陸軍指導者の間には「いかんともしがたい」という無力感が生まれていた。 一方、広島県は、東京大空襲が伝えられた3月末、『防空日強化実施要領』『人員疎開の受入れ』『罹災者避難実施計画』『退避指導要領』『非常時炊き出し計画』『警防団非常応援規定』等の通牒を逐次発し、県の防空体制の強化を図っていた。 更に広島市は、呉市での度重なる大空襲の教訓から、7月にデルタ地帯の市民に浮袋20万人分を配布し、河川の要所に筏を配置し、非常給食の準備をすすめていた。 各警察署も県警本部長の下で、「隣組」を中心に灯火管制、バケツリレー、ガスマスク装着等の、防空演習を指導していた。 また近隣の郡部は、広島市や呉市が被災した場合に備え、駆けつけ、救援に当たる「地区特設警備隊」を編制し、訓練も行っていた。 こうした状況を知った米国の雑誌は、「広島市の防空態勢は格段に強化され、ベルリンに優る世界一の防空都市である」との記事を掲載した(前掲の中国新聞が転載。原爆資料館でコピー可)。 しかしながら、惨禍は容赦なく襲った。 最大の要因は、日本では予測しえなかった原子爆弾の開発であり、その奇襲的使用であった。 逆に日本は、米国の技術開発の予測や急激な戦略変化を見落とし、「夜間・大編隊・焼夷攻撃」との先入観から抜けきれなかった。 当時の指導者やマスコミは、米国爆撃に対して「人と訓練で立ち向かえる」(朝日新聞17年1月26日)との精神主義を強調していた。 しかし日本国民の間には、度重なる防空演習や空襲警報に疲れ、「狼少年」現象が生じていたのも事実である。 呉市における空襲警報を例にとると、3月7回、4月2回、5月9回、6月3回、7月29回、8月12回、発令された。 警戒警報に至っては 226回を数え、一日に6回という記録も残っている。 終戦直後に来日した米国の『戦略爆撃調査団』は、「対米戦争中の日本人の士気の特徴」について、 ①初期、勝利による急激な上昇。 ②中期、戦争の長期化、戦勢の逆転に伴い、倦怠・損失・不安等により国防基盤が弱化。 ③後期、戦勢逆転による敗戦の予感、食料不足と疲労感、社会機構に対する疑義により士気低下が加速。 ④降伏まで完全な士気喪失には至らなかったが、戦略爆撃は進行中の士気低下に大打撃を与えたと、爆撃効果を自賛している。 日本の対応と比較されるのは、ドイツによる戦略爆撃・V2ロケット攻撃に4年も耐えた英国の対応だろう。 この間の英国は、?戦闘機・高射砲による防空戦闘、②戦略爆撃による対独報復攻撃、③学徒等の疎開と市民防衛による防衛、の3本柱で対抗した。 英国民の「粘り強さ、しぶとさ、執拗さ」に比べ、日本人の「熱しやすさ、冷めやすさ、淡白さ」が目につく。 また危機管理や抑止の面から見た場合、日本は敵地攻撃能力や効果的な阻止能力を欠いていた。 単純に英国と比較はできないが、国土防衛にあたっては、「盾」と「矛」の両輪なくして成り立たない。 このことは、核や戦略ミサイルに包囲されている現在の日本にも通じることである。 2 「人知を超える事態」に備える? 被爆当時、広島市の人口は28〜29万人、郡部から動員された義勇隊や朝鮮人徴用工が2万人、軍人が4万人と推測され、約35万人が被爆した。 市民は倒壊した家屋の下敷きとなり、或いは屋外に居て火傷を負い、瞬時に約5万人の死者・行方不明者が出た。 最終的には、総計10万人を上回る。(東京大空襲では 68660人、阪神・淡路大震災は6279人)。その結果、被爆直後、水を求めて川に入り死亡する市民が続出し、道路も死傷者で溢れていた。 救護計画に示された医療機関も致命的打撃を受け、18カ所の救急病院、32カ所の救護所は全滅。市内にいた医師 270人、看護婦Ⅰ650人の約9割が死亡または負傷した。ために、壊滅を免れた広島陸軍病院、赤十字病院、逓信病院に負傷者が殺到した。 爆心地周辺の建物も、爆風で一瞬にして倒壊した。 窓ガラスが割れる被害は、爆心地から27kmに及んでいる。 熱線による自然発火のため、市内2km圏で火災が発生した。 だが消防署職員も被爆したため消火活動は行われず、自然鎮火を待つだけだった。 午後4〜5時頃、火勢は衰えて自然鎮火したが、市内は一面焼け野が原と化した。 軍事施設も例外でなかった。 双葉町にあった第二総軍司令部をはじめ、爆心地に近い広島城址にあった中国軍管区、広島聯隊区司令部、兵站施設等は潰滅した。 本土決戦に備え司令部や部隊を急増したため、施設は既存の木造建築を利用していたためである。 また、市の中心部にあった県庁・市役所をはじめ、警察、消防、通信局、電話局、放送局等も大被害を被り、機能を喪失した。 指導者の面でも、第二総軍司令官の畑俊六元帥は出張で在京中、県知事は岡山に出張中で不在。広島市に居た県警本部長はじめ主要幹部も被災して死亡。 結局、救援にあたるべき中枢機能は、一瞬にして完全に破壊された。 では、なぜこうした未曾有の惨状になったか? 最大の原因は、想定を越える破壊力を持つ原子爆弾の前に、諸準備は役立たなかった。 3月10日の東京大空襲( 334機のB29 が来襲)を承知した広島県と市は、それぞれ防空本部を設けて大規模なB29の襲来に備えた。 その際、焼夷弾搭載150 機と爆弾搭載150機、計300機と想定していた。 しかし原爆の威力は、TNT火薬換算で約15キロトン、B29が搭載する通常爆弾の約3千機分に相当した。 市民の防空や空襲被害調査を担当する県警の新畑警部補をして、「これほど一度に市全体が火に包まれるとは思いもしなかった。計画は所詮計画にすぎなかった」と落胆させたのである。 では、人知を越える「不測事態」にどう備えるか? 阪神・淡路大震災直後、来日した米連邦緊急管理庁(FEMA)の副長官は「あらゆる可能性を考えて準備をするのが政治・行政の役割・・・想像を上回る自然災害といっても、想像しなかったこと自体が政治・行政の過失」と述べている。 しかしながら、想像はできても実行に移すハードルが高い。 その想像が余りにも現実とかけ離れたり、合理性を欠いたり、予算をオーバーすると見なされれば、採用・実行に進めない。 そこで次の対策として、万一の損害を考慮し被害局限措置を採る考えに至る。 欧米人の哲学は、「危機は人知を尽くしても避けられない」との前提から出発する。 そして、「起こり得る全てを洗い出し、いかに被害を最小限にくい止めるか」に知恵を絞る。 しかし日本社会には「人々を騒がせしてはならない」とういタブーがある。 「戦争や人災は起こるはずがない」とうい平和ボケも見られる。 そして「怖いことから目を背ける」思考停止に至る。 その結果、「最悪に備えよ」と説く人を戦争屋とののしり、有事法制を私権侵害と訴え、平和運動に逆らう者にタカ派のレッテルを張り差別する。 現在の問題である北朝鮮による『テポドン』発射に対しても、ミサイルを打ち落とすための技術や予算の議論は起こるが、大量破壊兵器を搭載したミサイルが落ちてきたとき、どうするかの議論は、マスコミからも聞こえてこない。 地方の政治家は、優しさや安心を強調するものの、危機に正面から向き合おうとしない。 「核を用いる」との恫喝にも、あえて不感症を装う。 3 非常事態下の軍隊と戒厳 沖縄作戦が始まった直後の4月7日、陸軍は第二総軍(中国・四国での本土決戦を指揮する組織)の司令部を、広島市街地北部の二葉町に設けた。 行政機構も『地方総監府制』(列島寸断時も地域毎の独立性を確保する広域行政機能)を敷き、中国地方総監に広島県知事をあて、非常時には軍の出動を要請する権限を付与していた。 被爆と同時に、第二総軍司令部や中国総監府の指揮機能は麻痺した。 だが、広島市南部の宇品に駐屯する陸軍船舶部隊と司令部(司令官佐伯文郎中将)の損害は軽かった。 爆心地から4kmの距離、比治山の存在、海風が幸いした。 以下、佐伯司令官が執った行動を、前述の『船防作命』等から抜粋する。 午前8時06分、佐伯司令官は窓から青白の強烈な閃光を感じ、ドーンという轟音を聴取。直ちに第二総軍、県庁、市役所に電話したが不通だった。 将校斥候を各方面に派遣した結果、市内各所で火事が発生し、道路は寸断され、各所に多数の死者・負傷者がいる事実を確認している。 8時50分、司令官は隸下の海上防衛隊長、野戦船舶本廠長、船舶練習部長、教育船舶兵団長、船舶砲兵団長に対し、市内の消火と負傷者救助を命令。 続いて広島船舶隊長に、患者を似島の検疫所へ輸送するよう命令。 10時00分、被害甚大なる第二総軍司令部に、救護班を派遣。 11時30分、中国地方所在の隸下部隊に対し、「日常業務ヲ停止シ、全力ヲ挙ゲテ広島市ノ復旧・救援ニ従事セヨ」と命令。 12時前、江田島の船舶練習部教育隊が来援した。直ちに、広島電鉄本社跡で負傷者の救護を命令。 13時20分、宇品地区の水道が減衰したので、江田島基地から濾過装置の輸送を指示。 14時頃、中国総監府の副総監が二葉山の防空壕に避難した第二総軍司令部を訪れ、中国総監との音信不通と、県庁、市役所、警察機関の全滅を報告し、事態収拾について軍への権限委任と罹災者の救援を要請。 これを受けた第二総軍は、既に救援活動の指揮をとっている船舶司令官を、「広島警備担任司令官」に任命すると確約した。 16時50分、船舶司令官は船舶倉庫長に罹災者救助のため乾パン、作業着、缶詰め等の交付を指示。 夕刻、船舶司令官は次の第二総軍命令を受領した。『船舶司令官ハ在広島部隊並ビニ逐次到着スル陸軍部隊ヲ併セ指揮シ、速ヤカニ戦災処理ニ任スヘシ。戦災処置ノタメ、警備ニ関シ在広島部隊ヲ区処スヘシ』 『中国地方総監・広島県知事及ビ広島市長ハ、予メ計画スルトコロニ従イ、速ヤカニ官民ノ救護給養並ビニ災害ノ復旧ニ任スヘシ。広島近傍ノ警備ニ関シテハ、船舶司令官ノ区処ヲ受クヘシ』 命令を受けた船舶司令官は、隸下部隊に救援・警備のため仮の担任区域を割り当て、一方で在広島の陸・海軍、官公庁に対し、翌7日午前10時に第二総軍司令部へ代表者を参集させるよう要請した。 7日午前10時、第二総軍主催の連絡会議が開かれ、それを踏まえ午後2時に船舶司令官が『広島警備命令(広警船作命第一号)』を発した。 これは、隸下部隊、海軍増援隊、中国憲兵隊、中国地区鉄道司令部、中国軍管区派遣部隊、中国地方総監府、県、市に対して担任区域を割当て、9日までに第一次の救護、死体の収容完了を指示する内容だった。 こうして被爆直後の救援活動について、指揮権が発動された。 ところが戦後、こうした軍による臨機の救援・警備活動に対し、一部の学者が「第二総軍は独断で市内に戒厳令をしき、軍政を開始した」と批判した。 だが、『船舶司令部命令綴』、『第二総軍命令綴』、佐伯司令官が著した『広島市戦災処理要綱の概要』、畑俊六元帥が記した『第二総軍終戦記』を見ても、「臨戦・合囲地境戒厳」や「行政戒厳」を示す用語はない。 また、第二総軍の命令も、行動は戦災処理と警備に限定し、行政権や司法権の行使に踏み込む内容はなかった。 ちなみに、戒厳の権限は帝国憲法でいわゆる「天皇大権」に属し、端末の司令官が発令しうるものではない。 広島市が昭和48年に編纂した『広島原爆戦災史』は、次の記述をもって船舶部隊の救援活動を、絶賛している。 「市中心部の陸軍諸部隊をはじめ、各官公庁が壊滅したなかにあって、宇品地区の船舶司令部・部隊だけでも残って勇敢に救護活動を展開したことは、惨禍の増大を防ぐ上で大きな役割を果たした」 4 迅速な復旧―軍・官・民の協力 被爆して焦土となったとはいえ、なお「本土決戦態勢」で中枢を占める広島市は、戦略上からも機能回復が急がれた。 その結果、罹災者の救護作業を含む一連の復旧活動は、軍・官・民の協同で昼夜の別なく続けられた。 一方、本土決戦準備の推進にあたる第二総軍は、終戦動向に翻弄されていた。 原爆投下の翌々日にソ連参戦が報じられ、9日には大本営から「本土決戦準備の推進と日本海正面の戦備強化」が指示された。 さらに、10日には廟議でポツダム宣言の受諾が決まり、13日に畑司令官は上京して元帥会議への出席を命じられている。 こうした状況で8日午後4時20分、第二総軍の命を受けた船舶司令官は、2回目の連絡会議を開き、『戦災復旧対策要綱』を検討した。 又、同日夜には陸軍省から派遣された災害調査班が加わり、原爆症状への対策を検討した。 その結果、9日の広島市における衛生機関は、陸軍救護隊30隊(約1300人)、海軍救護隊4隊、民側救護機関35隊(1隊は医師3、歯科医師1、薬剤師1、看護婦4〜10の編成)にまで回復した。 軍・警察・警防団による死体処理作業は、海中や焼け跡などの作業を残し、11日に一応終了している。 主要幹線道路上の雑多な倒壊物を除去し、トラックの通行を可能とする啓開作業には、県内各郡から派遣された地区特設警備隊があたった。 被爆の救援の召集を受けた呉、安芸、賀北、世羅、芦品、甲神、双三、比婆の地区特設警備隊(各1000〜1200人単位)は、6日午後から交代で救援活動を行っていた。 一方、罹災者に対する食料は、近郊町村からの炊きだしで賄われた。 広島市は呉市とともに重要都市として全県的な救援体制が敷かれており、各警察署の命令に基づいて食料運搬がなされるよう、予め計画されていた。 12日になると市内に食料配給所が開設され、野菜の配給も始まったが、配給量そのものが僅かだったため、罹災者は被爆の打撃に加え、飢餓にも襲われた。 14日、第二総軍司令部は二葉山に、中国地方総監府は三滝山に、県庁・市役所は己斐の山間部に、それぞれ疎開し、本土決戦に備えようとした。 だがこの日、政府はポツダム宣言の受諾を決定し、軍が保有する物資を払い下げて売却する方針を決めた。 一方、船舶司令部等の軍施設に収容されていた約1万5千人の患者も、県側の斡旋で廿日市、大竹、可部、忠海、竹原、西条、三次、庄原の警察署に1000人ずつ、海田市、広、河内、吉田の各署に500人ずつ割り当てた。 終戦の詔勅が下された8月15日、第二総軍司令官は船舶司令官が担任していた「戦災処置・警備」の指揮を解き、それらの責任・権限を県側に引き渡した。翌16日、全陸海軍部隊に停戦命令が発せられ、船舶部隊を含む在広島諸部隊の解散が決まった。 『広島原爆戦災誌』によれば、「この日までに軍隊が果たした救護・復旧作業は、遺憾なくその機動力を発揮し、被爆直後の大混乱の中にも、実に多大な成果をあげたが、この日を限って軍隊による救援復旧作業が停止された」と記述されている。 これを見るかぎり、被爆復旧における軍・官・民の協同は順調だった。 背景には、『防空法(民防空、昭和12年制定、16年・18年改正)』を中心に、関係諸法令が整えられており、内務省、地方総監府、県知事、市町村、軍隊の役割分担が律せられていた。 協同が順調だった第2の理由は、事前に準備された各種救援計画に基づき、訓練が確行されていた。 具体的計画や訓練実績がなければ、救援側は何をどうすべきかについて混乱するか傍観するにとどまる。 被災者側も無気力になって運命と諦めるか、暴徒と化して暴走する。 非常事態が突発した時、特定集団が自警団と称し自己中心の行動をとれば、秩序は崩壊して弱肉強食の巷と化す。 関東大震災における朝鮮人襲撃事件や、米騒動における焼討ち事件は、そうした状況が日本で起こったことを示している。 協同が順調だった第3の理由は、復旧活動にあたった船舶司令官が、関係機関を強権で統制する措置を避け、担当地域割りや役割分担を明示し、関係機関の自主性と特性を尊重したことである。 関係機関に、「運命共同体」「相互扶助」という雰囲気を醸成し、当面の食い物や宿舎を保証して奉仕に向かわせたと推測される。 こうした円滑な共同の背景には、?陸軍船舶部隊が即応態勢にあり、②自己完結性と特殊装備を持っていた点が挙げられる。 この部隊は、司令部の指揮・幕僚機能、手足となる実働部隊、隷下の病院、補給物資等を持ち、機動手段として小型ボートをフル活用し、デルタ地帯の小河川を利用した輸送・救護・連絡に努めた。 軍隊・自衛隊の自己完結性と即応性は、国防と災害への対応にとって不可欠の要件である。 おわりに ●軍隊指揮官と超法規行動。 見逃しえないもう一つの問題として、佐伯中将の救援活動開始の決断を振り返ってみたい。 船舶部隊がとった救援行動は、中国副総監の要請を受ける前に始まっており、第二総軍は後からこれを追認した。 8時半〜14時までの彼の判断と対応は、超法規行動なのか否かとの疑問である。 もともと船舶部隊に「広島市警備の任務」は与えられてない。 「参謀本部直轄」であり、広島地区の衛戍司令官ではなかった。 したがって、本土決戦に備えた準備が命ぜられていただろう。 そこで司令官は、参謀本部に連絡を取ろうとしたが、広島市内からの電話は通じなかった。 中央に対する特殊爆弾破裂の第一報は、呉の海軍鎮守府が報じている。 通信不能と知った時点で、司令官は救援活動を決断した。人道を優先した。 もしこの時、逆の決断―皇軍としての作戦準備優先―を下していたら、どうだったろう。 ソ連が満洲に侵攻した際、所在する日本軍が住民保護より作戦準備を優先した結果、戦後、関係者から怨嗟の声を浴びている。 佐伯中将の決断は、独断専行ではなかったし、軍令違反でもないと考える。 だが、その根拠は何だったか? また、佐伯中将が戦後も沈黙を保ったのはなぜ? 国防か人道かが競合した場合、優先すべきはどちらなのか? 本問題は、現代の自衛隊の超法規措置や、住民避難にも関わる課題である。 (2015.08.20) 帝国陸軍の戒厳や戦時警備に関する法令については、元戦史部長・現偕行社調査員の大東信祐氏陸自57にご指導を頂いた。紙面を借りて御礼申し上げるとともに、参考・補足事項を記述しておく。 ●平時の警備責任について。 陸自は、方面隊が「警備区域」の防衛警備を担任し、この区域を「警備地区」に分けて師団等に担任させ、更に地区を「警備隊区」に分けて連隊等に担任させている。 「隊区担当部隊長」は、近傍火災への出動は許されている。 また、隊区自治体の首長の要請を受け、警備・災害派遣を行う。 阪神淡路大震災以降、自主的判断に基づく派遣も可能になった。但し、師団長等への報告を要する。 旧陸軍の場合、「衛戍司令官」が陸自の「隊区担当部隊長」とほぼ同様の措置がとれるよう法体系が整っていた。(衛戍令九条) ●戦時の警備責任について。 広島被爆時、防空関係、沿岸警備の目的から、大本営は防衛総司令官→第二総軍司令官に「戦時警備の実施」を下令していた(20年7月11日)。 戦時警備とは、「戦時若ハ事変ニ際シ 軍事上障害ナカラシムル目的ヲ以テ 国内ニ於ケル軍事行動、重要施設、資源ヲ掩護シ 軍機ヲ保護シ、且所要ニ応シ治安ヲ維持スル為行フ警備」である。 これは、指揮系統を通じて行われるので「作命」で律せられた。 そのため、緊急事態において、文書命令は実際の行動より遅れる、口頭命令→文書命令で追認という形式は起こりうる。 陸自の場合、戦時を律する法律体系がない(憲法に非常事態や国防条項がなく、勅令制度もない)ので、超法規措置で対応するか、立法措置を待つか、平時の法体系を準用するかで対応することになる。 したがって、作戦上・人道上、急を要する場合でも、グレーゾーン事態対応、超法規的対応は起こりうることになると思われる。 参考とした史料・文献 1 戦史叢書『本土防空作戦』、『本土決戦準備 2』(朝雲新聞社) 2 広島市『広島原爆戦災史 全5巻』(広島市、1971年) 3 広島県『広島戦戦災史』(広島県 1987年) 4 航自幹部学校翻訳「戦略爆撃調査団報告書」防衛研究所戦史資料 5 「第二総軍命令綴り」防衛研究所戦史資料 6 畑俊六元帥「第二総軍終戦記」防衛研究所戦史資料 7 井本熊雄大佐「広島原爆被災時の第二総軍司令部の状況」防衛研究所戦史資料 8 「船舶司令部命令綴り」防衛研究所戦史資料 9 佐伯文郎中将「広島市戦災処理の概要」厚生省復員局 10 日本の空襲編纂委員会『日本の空襲 7・10巻』(三省堂、1980年)
|
||||