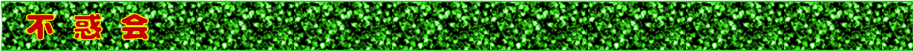
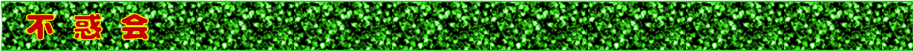
⑥
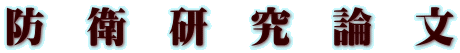
| 6 国民動向―戦うべきときに戦わねば滅ぶ 戦闘が始まるや、日本の朝日新聞は「英国民の間に厭戦・停戦といった気分が充満している」との報道を繰り返した。シェフールドがエクゾセ・ミサイルによって大破した翌日の見出しは、「両国民にえん戦気分」となっている。同じ日付のロンドン発の見出しも、「英沈痛」「顔こわばらす将官」「安否を気づかう妻や母」の文字で埋められた。 5月7日付『素粒子』欄は、「氷の海に戦う、わが子の安否はいかに。春はまだ浅き軍港ポーツマスに、岸壁の母たたずむ」と感傷的だ。5月14日付には、左手に子供を抱え、右手で涙を拭っている婦人の写真に添え、「3,000人の兵士を乗せてフォークランド諸島沖へ向け、英国サウザンプトン港を出航したクイーンエリザベスⅡ世号を、涙ながらに見送る家族たち」と説明している。更に、英軍のフォークランド上陸を報じる5月24日付にも、英国『フォークランド平和委員会』が停戦交渉を求め、5,000人規模のデモ行進が行われたとの記事を、写真と共に掲載した。だが現実の英国民は、朝日新聞が報道する和平・政治解決とは裏腹に、日がたつにつれサッチャー首相の強硬・軍事解決の下に結集した。英『エコノミスト』誌が4月17日、24日、5月8日号に掲載した世論調査の結果は、それを明白に裏付けている。 4月2日 アルゼンチン軍約 400名が フォ-クランド島に上陸し、英総督は降伏。 3日 英政府は空母インビンシブル を中心とする艦隊の派遣を決定。 国連安保理は、敵対行為の中止、侵攻軍の即時撤退、外交解決を決議。 25日 英軍は南ジョージア諸島を奪還(マスコミのリークを追認)。 5月2日 英原潜がアルゼンチン巡洋艦ヘネラル・ベルグラ-ノを撃沈。 4日 英駆逐艦シェフィ-ルド がアルゼンチン空軍のミサイル攻撃を受けて大破。 5日 米国とペルーによる仲介は不成功。 21日 英軍が東フォークランド島に上陸。 6月14日 ポートスタンリーのアルゼンチン軍は降伏。 質問の内容 → 政府の対応 将兵の犠牲 奪還作戦 アルゼンチン爆撃 4月14日 英空母派遣 満足 60% 肯定 44% 肯定67% 賛成 28% 4月21日 ジョ-ジア奪還予測 68% 50% 65% 34% 5月4日 シェフ-ルド大破 71% 53% 72% 38% (出所:漆山成美 『国際紛争と世論』90~92頁) 更に戦闘終了直後、「この紛争で英軍は 256名の将兵を失い、7億ポンドの経費を要したが、機動部隊を送るべきだったか」という質問に、肯定する意見が76%と圧倒的で、「送るべきではなかった」の22%を凌駕した。また、「フォークランドの主権確保は非常に重要だから、その防衛に要する陸・海軍のための増税に賛成するか」という厳しい質問にも、増税を肯定したものが71%、否定したものは24%にとどまっていた。アルゼンチンの侵攻前、係争問題でぎくしゃくしている間、英国民は国防負担を増額したり、将兵の生命を危険に晒す価値はないと考えていた。ところが、アルゼンチンから不正の攻撃が加えられるや、アングロサクソンの考えは一夜にして切り替わった。ではなぜ英国民の間に、反戦や平和運動が広がらなかったのだろうか。 第一は、「力」を巧妙に用いる伝統である。今も昔も小国である英国は、本土における食料確保と海外との交通路の確保を自己保存の原則としている。「パックス・ブリタニカ」と呼ばれた時代、それを支えたのは卓越した海軍力と、世界に広がった海外領土と、商業・産業立国としての経済力であり、国際社会の秩序維持と英国本土の生存・繁栄のため、相手の出方や状況に応じ「力」を巧妙に用いた。すなわち、平時は「力による外交=政治的・間接アプローチ」、有事は「力による和平=軍事的・直接アプローチ」である。アルゼンチンがフォークランドに侵攻した時、『鉄の女』と呼ばれたサッチャー首相は下院で答弁し、アルゼンチンの軍事政権を「侵略者」と呼び捨て、「世界が立ち上がらなければ、英国が先頭に立って侵略者から民主主義と自由を守る」と宣言した。シェフールドの大破という悲劇や、民間船を徴用した長距離遠征の困難にもかかわらず、英国民はこの時点で「政治アプローチ」が既に無力であることを経験的に知っていた。 第二は、参戦という国家への奉仕が、「犬死」ではないという共通認識が存在した。英国民の間でも、男性的な「国家の原理」と、女性的な「家族の原理」は対立する。男は妻や子に後ろ髪を引かれながら、また自らの意思に反しながらも敢えて「国家の原理」に生きんとして戦いに臨む。これに対し女は、息子や夫が戦場に赴くのを嫌い、あくまで生命の尊重に生きんとし、戦争の悲惨さを訴えて家族を守り抜こうとする。だが、国家のために戦死したとしても、なお魂は永遠なるものの中で、家族の将来を末永く見守って、その幸福を願うことが出来るという価値観が現存する。エリザベス女王は、海軍中尉であり、対潜ヘリの乗務員であるアンドリュー王子の参戦や戦闘行動を許したし、サッチャ-首相は終戦直後の7月に犠牲者の追悼をセントポール寺院で執り行い、翌年1月(夏期)には戦場を訪れて花輪を捧げている。 第三は、平和運動からは何も生まれないという考えが、定着していた。戦争の悲惨さを訴える反戦・厭戦運動が大衆動員につながり、政治判断を狂わせたことはベトナム戦争や欧州での反核運動で実証ずみだった。反戦平和論は、国家が持つ矛盾や人間存在の本質に根ざす性悪性の直視を避け、ただ「平和は善、戦争は悪」と叫ぶだけで、それ以上のことを考えようとせず、いつも自己欺瞞に陥ってきたのである。このような平和主義の下では、人々は危険に対する感覚を失い、脆弱化し、領土と国民を他国の犠牲に供することになる。そこからは、被征服という屈辱しか生まれない。反戦運動や平和主義の限界を承知し、第一次・第二次大戦前の「悲惨な平和」を体験している英国民は、紛争解決に「話し合い」を求めようとしなかったのである。 「領土問題を軍事力によって解決しない」ということは、第二次大戦後の国際社会で重要な原則となっている。だが、相手が急迫不正の侵害を行ったり、あるいはその兆しがある場合、迅速に対処する行動も「ルール違反者に対するペナルティ」として、国際社会が認める原則である。フォークランド紛争では英国が、湾岸戦争ではクウェートが、後者の原則に基づく対応を怠ったため、国際社会に混乱をもたらした。フォークランド紛争から学ぶべき最大の教訓は、毅然とした対応をとる意思と能力を保持し、紛争を未然に防止して国際社会の責任を果たすことであり、それが「無益な戦争」や「戦う必要のなかった戦争」を防ぐ唯一の方法だということである。 (2011.03.10 大震災前日に校了しました) |