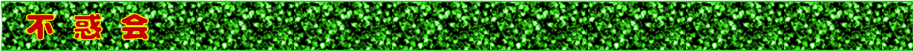
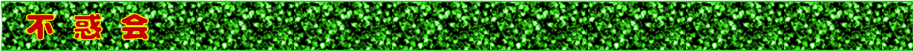

喜田 邦彦
6 区 隊 職種:普通科
オバマ発言で尖閣は大丈夫? 本年4月、オバマ大統領はリバランス政策を引っ提げて日本、韓国、マレーシア、フィリピンを訪問した。 日米首脳会談では、歴代米国大統領として初めて「尖閣諸島は、日米安保条約第5条の適用対象」と明言した。 また、他の同盟国や友好国首脳に対しても、コミットメントすると約束した。 だが同時に大統領は、日本を含む同盟国に対し、中国への刺激的言動を控えるよう念を押した。 また政権は、安倍首相の靖國神社参拝に、「失望する」とコメントした。 これは、同盟強化を確認する一方で、中国に保険を掛け中国との間で「新しい形の大国関係」を維持していこうとする二股路線の始まりと受け取るべきではないか。 思い出してほしい。1972年、ニクソン大統領は頭越しに北京を訪れ、西欧と日本をあっと言わせた。 最近も、尖閣沖での中国漁船体当たり事件で、船長の早期釈放に圧力をかけたのはクリントン国務長官(当時)だった。 大国・米国は、世界情勢・戦略から発想し、国際秩序と国益を追求する。 安倍首相は、集団的自衛権の限定行使で同盟の片務性を修正し、日米防衛協力の指針(ガイドライン)で、グレーゾーン事態における役割分担を定め、離島防衛を強化しようとしている。 だが日米安保は、NATOのような自動介入条項はない。 第5条で「各締約国は・・・自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処する」と規定されている。 日本側には、「自動介入や集団的自衛権に歯止めをかけねば、米国の戦争に巻き込まれる」反面、米国の都合から「見捨てられる」というジレンマがある。 一方、世論の国・米国にも、「小国の領土紛争に巻き込まれたくない」「大市場である中国との衝突は避けるべし」との意見が根強い。 「人の住んでない島のために介入するほど愚かではない」と米国世論が盛り上がれば、日米同盟は一気に醒めよう。 米国議会も、「グレーゾーン事態は、日本有事に該当せず。相互拘束の例外、不確実性は都合が良い」と見るかもしれない。 さらにここにきて、ロシア・プーチンと中国・習近平の「力による国境線の変更」が始まった。 クリミア併合に際しプーチンは、原潜3隻をカリブ海に派遣したと伝えられる。 沖縄海兵隊をグアム・豪州に後退させたのは、中国の新型核兵器への対応措置と見える。 米国にとって日本の戦略的重要性は、冷戦期に比べ軽減している。 こうした時期にこそ、米国の「核の傘」や「共同対処」を担保する施策が必要で、日本側の思考を「グレーゾーン対応」という矮小な範囲にとどめるべきでない。 シリア・ウクライナ・南シナ海の抗争を見ても、米国が世界の警察官でないことは明白である。 オバマ大統領の「尖閣安保適用発言」に安どすることなく、むしろ「米国をいかに巻き込むか」について、日本の知恵と施策が求められている。 以上の問題意識から、危機において軍事小国が如何にして大国を巻き込んだかを検討したい。 ケーススタディとして、失敗と成功の4例を紹介する。 ①第2次大戦(WWⅡ)で本格侵攻の危機に直面した仏国が、米国・英国との連合に失敗したケース。 ②同じ大戦初期、米国を巻き込んだ英国の政策過程。 ③戦後、離島に奇襲侵攻を受けた英国の介入要請と、米国の消極的対応。 ④化学兵器の脅威下でミサイルを撃ち込まれたイスラエルが、米国を振り回した例である。 いずれも「米国と特殊な関係」とされる国家の同盟であり連合作戦だった。 危機において軍事小国はいかにして米国を巻き込んだか 検討ケース
WWⅡにおける仏国と米・英・・・仏国の同盟・連合は何故失敗したか? 本ケースの特徴は、①脅威―本格侵攻が迫った事態、②対処―準備に時間の余裕がある、③同盟―共同対処の基盤がない、④結果―同盟・連合に失敗して敗北した、点である。 (1)専守防衛と抑止力の低下 WWⅡ直前の仏国の「マジノ戦略」は、日本の「専守防衛」と似ていた。 対独防衛線は国境の連続要塞(日本は領域防衛)。装備体系は重砲重視で、戦車・爆撃機の攻撃兵器は持たない(日本は敵基地攻撃力を持たない)。 作戦開始は「待ち受け」で初動は議会承認を要し、先制攻撃を否定(日本は戦略守勢に徹する)していた。 但し兵制は、国民皆兵のアマチュア大衆軍(少数精鋭の志願制)で、その数は大戦直前に80万から40万に漸減してはいたものの、国民や指導者は「陸軍大国」と自負していた。 ところがドイツにヒトラーが誕生し、大規模な再軍備を始め、非武装地帯に軍をすすめ、オーストリア併合に乗り出した。 戦争放棄の平和主義は、自らが戦争を仕掛けないのはいいとしても、相手が敵意を持つ場合、それを助長する。 さらに、アマチュア大衆軍と要塞と火砲中心の国防態勢では、ヒトラーの冒険を抑止できなかった。 仏国参謀本部が検証した兵棋演習でも、ベルリンに突進する機甲攻撃能力を欠き、ライン川を渡河する器材はなく、部隊を輸送するためには車・馬匹の総動員が不可欠で、パリ防空の対空戦闘能力すら持たず、「軍備体制の改革」を政府に強く求めていた。 仏国政府も参謀本部とそうした認識を共有したが、自主防衛を強化する軍備改革に向かわず、伝統的「同盟政策」に向かった。 戦争放棄の平和主義と、「軍による平和」より「軍からの平和」を優先した。 ドゴールによる少数精鋭の機甲打撃部隊の創設案は、クーデターの恐れありとして政治家や国民から嫌われた。 仏国政府は、チェコスロバキア・ポーランド・ルーマニアとの同盟(主に軍事援助)で「対独包囲・態勢の優越」を図ろうとした。 しかし国境要塞と重砲による防勢作戦では、協同作戦や遠征軍の派遣はできない。 それを見越したポーランドは、ドイツとの不可侵条約締結を企図し、仏国と距離を採り始めた。 やむなく仏国は、ソ連と攻守同盟を結んだ。 だが陸軍は共産主義に反対で、合同の会議や自国演習へのソ連武官の観戦を拒否した。 また東欧諸国は、ソ連軍の自国通過を拒絶した。 仏ソ同盟の破綻を知ったヒトラーは、オーストリア併合に向かったのである。 こうした情勢で、仏国軍人の中には「ヒトラーとことを構えるより宥和策を取るべし」という敗北主義が起こり、ヒトラーは「仏国陸軍には反撃の意図や能力に欠ける」と公言し、仏国国民の分裂・混乱・敗北主義を煽っていた。 (2) 仏国の介入要請と米国の拒否 当時の米国は、国際連盟の創設を推進したものの「非加盟・中立」で、ルーズベルト政権も欧州大陸への不干渉政策を採っていた。 一方英国は、ヒトラーに対し宥和政策で臨み、陸軍大国・仏国との連携に乗らなかった。 同盟政策に行き詰まった仏国政府は、秘密裏にルーズベルト大統領に新型爆撃機の開発・購入を要請した。 今でいえば大量破壊兵器に匹敵する起死回生の抑止・戦略兵器であり、国連では都市爆撃の禁止が真剣に検討されていた。 中立なので兵器輸出ができないルーズベルト政権は、この開発・売却を商業ベースで受け入れ、カナダで部品を組み立て輸出しようとした。 だが大西洋をいかに運搬するか、軍事機密の売却が可能かを検討中、試験飛行で墜落事故が続き、断念に追い込まれた。 ドイツのポーランド侵攻でWWⅡが始まり、翌年春にノルウェー・オランダ・ベルギー・仏国が奇襲侵攻を受けた。 西部戦線が1週間で突破され英仏連合軍が窮地に陥ると、米国内ではさすがに「英・仏を援助すべき」との声があがりはじめた。 しかし米国議会は、英仏連合軍の健闘が米国の安全に不可欠という点に疑問は抱かなかったものの、孤立主義の壁は厚かった。 2週間で英仏軍がダンケルクに圧倒されたため、仏国政府は米海軍による緊急介入を要請した。 だが米国議会は、「対独宣戦」(宣戦布告は議会の専権事項)を問題にならないとして取り上げなかった。 政府内でも、「仏国は絶望的」との見通しから、関心は英・仏艦隊の敗戦後の処理に集中した。 もしそれらがドイツに捕獲されれば、大西洋の安全は脅かされ、米国にとって「対岸の火事」ではなくなる。 米国政府は敗色濃い仏国に「残存艦隊のドイツへの引き渡し拒否」を要請した。 これに対し仏国首相は、艦隊保全のため米国艦隊の派遣を再度要請した。 しかしルーズベルトは、これまでの戦闘における仏国人の勇気を賛え、被占領下における抵抗運動を期待し、可能な範囲での援助を約束するとのリップサービスにとどまった。 5週間後に仏国は降伏し「独仏休戦条約」を締結したが、仏国艦隊は仏領北アフリカに遁走して引き渡しを免れた。 米国が介入要請を断ったのは、①介入の意図(議会承認)も能力(海軍軍備)もなかった。②双方に同盟・連合の基盤・準備がなかった。③米国世論は「孤立・中立の幻想」にとりつかれ、介入の「大義」がなかった。④介入に伴うリスクやコストについて、仏国から提案がなかった。⑤何より敗色が濃かった。 負け戦に加担はしないのは世の習いである。米大統領は、英国に対する軍事協力についても、極めて用心深く接近することになる。 (3) 仏・英連合の疑心暗鬼 ヒトラーがミュンヘン会談の合意を破ってチェコに侵攻した時、英国は宥和政策を放棄して仏国との連合に転換した。 「英国の国防線オランダ」にヒトラーの脅威が及んだためである。 連合の準備会議で仏国が英国に要求したのは、第一に兵力不足の解消だった。 WWⅠで85個師団を派遣した英国の実績から32個師団を要請し、英国をあきれさせた。 大急ぎで陸軍増強に乗り出した英国は、ようやく10個師団を復活したばかりだった。 第二は敵地攻撃力・機甲打撃部隊の派遣である。 仏国はマジノ要塞戦で「盾」の役割を担い、「矛」の役割を英機甲部隊・英空軍に期待した。 だが英国は、虎の子である機甲師団の派遣を最小限にとどめ、空軍主力の派遣はロンドン防空を優先するとして拒絶した。 第三は作戦地域の推進である。 仏国は、国境防衛では国土が疲弊するとして、戦場予定地をベルギーに推進するよう求めた。 オランダの防衛が本土防衛の最前線と見る英国は、受け入れた。 第四は、「開戦の引き金」である。 ドイツが侵略に出た場合、「待ち受けの」仏軍の「第一撃」は議会承認を得ねばならない。 日本の防衛出動と国会承認と同じ関係である。 そこで英国に開戦の引き金を引かせることで、議会承認をクリアーしようとした。 双方の利害対立の調整は、ドイツのポーランド侵攻が「時の氏神」になった。 同盟国ポーランドから、「対独宣戦布告」と「牽制作戦」を求められた英・仏両国は、「同盟義務の履行」と「本格戦争の回避」のジレンマの中で、結局、一兵・一機・一発の戦力も送り込まず、西部戦線での牽制作戦も行わず。ワルシャワ崩壊を黙認したのである。 防勢の連合作戦は、相互不信と疑心暗鬼から摩擦が生じやすい。 仏国の自助努力の不足を察知した英国は、最小限の陸・空軍力を仏国に派遣する一方で、「ドイツとの単独講和禁止協定」を強要し、仏国海軍を英海軍の指揮下に置くよう求めた。 仏国が降伏してドイツに艦隊が拿捕された場合、英本土が危険に晒されるからである。 作戦前の屈辱的要求であり、仏国を信用していないゆえの要求が明白だったが、仏国はこれを飲まざるを得なかった。 しかし結局、英仏連合軍は3日で国境線を突破され、3週間でダンケルクに包囲され、5週間でパリは陥落した。 相対戦力は同等だったにもかかわらずである。 英国が心配した通り、仏国は単独で降伏した。 艦隊は無傷だったが、ドイツに拿捕される事態を恐れた結果、残存艦は自沈を命ぜられるという悲惨な運命に見舞われたのである。 (4)攻撃なき防御で国防は全うしえない 仏国は「専守防衛」の欠陥を連合作戦で補修したはずだった。 だが、防勢に偏った国防体制と硬直的な作戦指導、国家指導者の対英期待と敗北主義、国民の「マジノ神話」過信と無気力さは、「専守防衛」がもたらした後遺症であり、自滅だったことを示している。 戦後の仏国の国防政策は、こうした失敗を踏まえたドゴール将軍の信念から生れている。 戦争前の彼は、ドイツを抑止するため「機甲打撃部隊」の創設を訴えたが、国民は職業軍を嫌い、政治家は「マジノ戦略」に固執し、高級軍人は火力阻止が万能と考えていた。 戦後、第五共和制の初代大統領に就任した彼は、1959年に国民投票で憲法を改正し、第三共和国憲法の「戦争放棄」精神は尊重するとしながらも、新憲法から削除した。 また、「仏国は自分自身によって、自分自身のために、自分のやり方で国を守る」との国防哲学に基づき、最小限の核戦力を保有し、NATOの軍事機構から脱退した。 こうして、「専守防衛」政策は完全に転換され放棄されたのである。 盟主・軍事大国といえども、死活的国益が脅かされない限り進んでリスクを引き受けることはない。 泥縄で付け焼刃の連合作戦が失敗に終わった背景には、双方に信頼関係が欠けていた。 自助努力の重要性を再認識し、同盟や連合作戦を補完的役割と位置付けるべきであろう。 自前の「矛」や敵基地攻撃能力を持たない軍隊は、自力で国防を全うしえない。 専守防衛でも、同盟政策でも、「矛」の一部は欠かせない。 さて、わが国の「専守防衛」はどうか。 昨年末の国家戦略・防衛大綱・中期防で新たな方向を打ち出したが、憲法改正の敷居は高く、集団的自衛権の行使やグレーゾーン事態への対応について、国民の反対は強いようだ。 「専守防衛」の呪縛は続いている。 結局、従来のガイドラインにあるように、日本の戦略・装備・運用上の欠陥を米軍で補おうとするだろう。 しかし、これまでガイドラインが存在したにもかかわらず、北朝鮮は核兵器を開発・保有し、中国はガス田盗掘や原潜による領海侵犯等を続けている。 役割分担という言葉に惑わされず、独立国として持つべき機能は自前で保持する努力が必要である。 それこそが本当の「基盤的防衛力」と言うことではないのだろうか。 WWⅡにおける米英・・・英国はいかに米国を巻き込んだか? 本ケースの特徴は、①脅威―敵による爆撃・侵攻準備が始まり、②対処―存亡の危機に陥ったが準備は遅れており、③同盟―周辺国の敗北で孤立を強いられ、大国との同盟基盤はなく、④結果―ギブ&テイクで大国を巻き込み、連合作戦に道筋をつけた点である。 (1) 米英関係の本音と建て前 ダンケルク撤退でかろうじて生き残った英国は、「孤立無援で対独戦を遂行するか、ドイツと屈辱的な和平に進むか」の選択を迫られた。 チェンバレンに代わって首相に就任したチャーチルは、「戦力を急増・再編して反攻まで時間を稼ぎ、持久してナチス体制の内部崩壊を待つ」との主戦論と、英国伝統の間接戦略を主張した。 この時点、1940年4月、英国の軍備は極めて厳しかった。 本土には緊急造成した10個師団しかなく、5月にダンケルクから撤退した部隊は装備を失い、ドイツの英本土上陸作戦(あしか作戦)の前哨戦であるBattle of Britainが始まろうとしていた。 チャーチルが望みを託したのは米国である。 国民向け演説で、「新世界が全力を挙げ、旧世界の救援と解放のため馳せ参じるまで戦おう」7と結んだ。 彼の頭には、「窮地にあるとはいえ英本土は米州大陸の防波堤、米国にとって戦略的資産であり、その存亡に安閑として居られないはず」との考えがあった。 大陸勢力の大西洋進出に立ちはだかり、反攻・攻勢の際はステップとなる英本土の役割を、米国に高く売りつけようとした。 英国の地政学的な戦略価値は、大陸に対する日本列島と同じであり、前方展開拠点として米軍のアジア戦略を補完することができる。 そこでチャーチルは、160万の国土防衛隊・国防市民軍の創設に乗り出し、彼らに渡す軽装備の購入を米国に求めた。 要請を受けたルーズベルト大統領は、中古の小銃50万丁、75㎜野砲5百門、大量の弾薬・砲弾を、武器でなく雑品扱いで民間会社に払い下げた。 米大統領は計算ずくだったし、「中立」を守れと叫ぶ米国議会も「対英武器援助で英国人に戦わせて対岸の火事を見つめる」代理戦に、反対しなかった。 国民は、自分たちの息子が徴兵で欧州戦場に投入されることを、何より嫌っていたからである。 (2) 米国の代理戦争と能力審査 だが米国政府は、大量の武器を売却して資金が回収できるかを問題にした。 ケネディ駐英大使は、英国軍備の決定的立ち遅れ、ノルウェー・ダンケルクからの撤退、ポンド相場の著しい下落と信用低下から、英国経済の破綻を予想した。 彼の悲観的な見積りは、ルーズベルト以下政府の対英支援を躊躇させ、チャーチルの怒りを爆発させた。 また、米国陸・海軍も「対英武器援助より、米軍自体の強化を優先すべし」と大統領に進言した。 こうした情勢でルーズベルトは、「Battle of Britainにおける英国の抗戦意欲・進攻対処能力を見極める必要がある」として、陸海軍混成の調査団をロンドンに急派した。 英国の「抗戦意欲」は、国王とエリザベス王妃が「英国を離れない」と声明したことで、「仏国の様な敗北主義の雪崩現象は起らない」と保証した。 英軍の「継戦能力」については、英国陸・海軍が米国調査団にそれまでの作戦計画を開示し、弱点や問題点を率直に伝える態度をとった。 さらに、スピットファイア戦闘機・レーダー・アスディック等の最新兵器の開発・運用状況を見学させ、対独戦から得た貴重な経験と教訓を米側に開示した。 こうした状況を把握した米国調査団は、結論として「英国は持ちこたえる」と判断し、英国存続のため当面の課題が「大西洋での米海軍による船団護衛の肩代わり」だと報告した。 1940年10月、これらの報告が大統領に届けられ、またBattle of Britainで英国の勝利が明らかになった。 米国の審査に英国は合格したのである。 (3) 米国を巻き込む方策 「米国を巻き込む」には、まず「中立」を転換させねばならない。 そこでチャーチルは、米国に50隻の旧式駆逐艦の貸与を要請した。 ドイツのUボートがオランダ~仏国の港湾から出撃しており、米国からの軍需品と英連邦の食糧を運ぶ英国船舶の喪失が急増していた。 チャーチルは、船団護衛の駆逐艦建造を急がせる一方で、完成するまでの対策として旧式駆逐艦の貸与を米国に申し入れた。 はじめ米国政府は、老朽艦ですら兵器であり、「中立」の壁があると渋った。 しかし、大戦後の大西洋制海権の奪回をもくろむルーズベルトは、大西洋・カリブ海にある英領諸島に米軍基地の設置を認めるなら、憲法上の障害は回避しうると回答した。 英国の大西洋における制海権は、「艦隊・商船隊・基地群」から成り立っており、英国王室や議会は当初領土の割譲に猛烈に反対した。 だが、英国存亡の折から米国提案をやむなしとし、首相支持を決議した。 チャーチルの狙いは、「武器譲渡に伴う米国の非中立国への実質的転換」であり、連合に巻き込むための踏絵としたのである。 「巻き込み」の次は、逃がさぬよう「拘束」することである。 チャーチルが放った第二の矢は、大規模の「借金」要請だった。 開戦時に英国が保有した「金」と「外貨」はわずか45億ドルで、米国に発注した軍需品は巨額にのぼり、1940年12月に現金決済は不能となっていた。 11月に大統領3選を果たしたルーズベルトは、チャーチルの要請を検討した結果、「武器貸与法案」を議会に提出し、「米国は民主国家の一大兵器廠」になる必要があると国民に訴えた。 大きな借金を持つ企業や国家は、潰したり見放すことはできない。 米国での法案審議は紛糾したが、1941年3月末に成立し、総額40億ドルが英国に割り当てられた。 借款は武器購入にとどまらず、食糧売却費、英艦船建造・修理等に拡大されたため、ますます膨れ上がった。 そのため米国は、戦時中は財務長官を英国に派遣して財政事情を逐一報告させた。 後に、ルーズベェルトが死去してトルーマンが登場するや、対英借款は直ちに打ち切られた。 借金返済能力がないと見れば、納税者に説明できないとして、対英援助を打ち切った。 米英間といえども、カネについては非情である。 (4) 英国のバーゲニング・チップ 英国にとって次の課題は、軍事面の結びつきであり、共同者としての信頼獲得である。 そのためチャーチルは、WWⅠから培ってきた軍事科学技術情報の米国提供を命じた。 ハード面では、マグネトロン、ジェットエンジン、化学兵器、船舶防護装置、対潜水艦装置等の図面やデーターの提供である。 当時、これらの技術情報は圧倒的に英国優位で、チャーチルは「米軍がその技術水準を高めることは、英国の利益に合致する」と考え、米国の軍事協力・ゆくゆくは連合作戦の代償として売りつけたのである。 さらにソフト面でも、米大統領の要求に基づき、次の情報や便宜の提供を命じた。 ●原爆開発 英国研究者はチャーチルに、「この分野での英国の先行利益は保護しなければならない」と訴え、米国との共同研究を拒否したが、米英首脳会談で提供が決まった。 ●暗号関係英国は、ポーランド・仏国から得たドイツのULTRA情報と解読機を米国に提供した。一方米国は、日本・伊国の暗号解読の進捗状況を明らかにしたが、この分野でも英国の情報蓄積がはるかに進んでいた。 ●英領基地の使用 大西洋輸送ルートの掩護・中継基地となるグリーンランド・アイスランド・アゾレス諸島等は、ドイツの事前占領を回避するとして、基地使用を容認した。 ●船団護衛 Uボートに対する商船隊護衛のノウハウは英国が優れていたが、米海軍が西大西洋航路を警戒して英国海軍の肩代わりをするため、英国はそれを提供した。 こうした英国のバイタル分野における協力の見返りとして、米国は訓練の受託(英国空軍操縦士・乗員に対する米国製爆撃機の飛行訓練)、艦船の修理(損傷した英軍艦の米国での修理施設の提供)で英国を支援した。 ギブ&テイクの軽重は単純に評価できないものの、大戦初期における両国の力関係を表しており、米国側は「連合の証」と見て評価した。 これに対し英国議会には、「持ち出し」と見る不満が残った。 (5) 軍事協定による連合への拘束 同盟や連合を機能させるには、戦略ドクトリン、兵器体系の調達と配備、兵力運用の基本と配置、意思決定手続き等、共有しておく必要がある。 つまり機能発揮のための制度化だが、それにより同盟・連合の信頼性・拘束性が強化される。 チャーチルは、訪英中の米国軍事使節団に対し「枢軸国に対する努力の統一」のため英国三軍代表と米国陸海軍代表の非公式会談を提案した。 英軍の能力と意図を信頼し始めた米国軍事使節団は、その必要性を認めて大統領に報告した。 これを受けたルーズベルトは、「米英軍事会議(American-British Conversations)」を許可し、1941年1月29日からワシントンで始まった。 開催に先立ち大統領は、次の指針を米軍部に与えている。 ①対日問題が切迫しても全努力を対英武器援助に集中し、対独作戦・欧州戦場を優先する。②米海軍は大西洋での英国船舶の護衛と哨戒活動を準備する。③米陸軍は戦力が充実するまで積極行動には出ない。 しかし、米国は未だ「中立」のため、「ABC1協定」は議会の戦争権限を犯す恐れがあるとし、正式承認を控えた。 だが、米軍部はこれを米国参戦後の「連合作戦大綱」とみなし、「米国陸海軍統合戦争計画」に組み込んでいる。 (6) 介入の大義名分と戦争予行 次にチャーチルが打った手は、ルーズベルトに呼びかけて枢軸国との戦いの大義を明確にする「大西洋憲章」の公表である。 「米国を参戦に踏み切らせたい」と考える彼は、共同宣言に「ナチス専制政治の撲滅」を含めさせ、世界の諸国民に「米国が挑戦に乗り出す」と受け取られる共同声明を用意した。 1941年秋、日米交渉が破局に向かいつつある状況で、大西洋では米海軍が「非宣戦の戦争(Undeclared War)」の準備を進めていた。 ドイツ潜水艦の英国船に対する攻撃と、英国駆逐艦による反撃が激化する情勢で、米国は海軍の任務を「敵船の(英軍への)通報」から「発見次第発砲」へ切り替えた。 また、米国商船の撃沈が続いたことから「中立法」を修正し、商船の武装化と船団護衛を米艦隊が肩代わりすることを許した。 これらは、「ABC1協定」に基づく英米の「戦争に近い協力」であり、連合作戦の予行でもあった。そしてそれを恒常化させるため、米陸海軍の常設機関がロンドンに設けられ、英三軍幕僚長委員会との定期協議が始まった。 日本の真珠湾奇襲に伴い、米国議会は対日・対独の参戦を承認したが、チャーチルにとっては喜びであり不安でもあった。 米国が戦力を対日戦に振り向け、欧州正面を英国任せにする事態を懸念したのである。 そこでチャーチルは、「連合戦略の基本」と「戦争指導機構」についてルーズベルトに確認する必要があると考え、三軍幕僚長を伴って米国に向かった。 こうした情勢で、「ワシントン会議」と呼ばれる「連合国最高戦争会議」が始まり、「連合戦略の基本原則」(ABC4)が合意された。これが先例となり、6カ月ごとに連合国最高戦争指導会議が開かれることになった。 チャーチルの首相就任から17カ月である。 一般に米英の軍事協力は、「特別関係」と言われている。 しかしWWⅡにおける米国の協力は、ルーズベルトとチャーチルが「ライオンとキツネ」と比喩されたように、「危機に陥った英国を救う」単純目的ではなかった。 ルーズベルトは対英援助を梃に欧州政治への介入に道を開き、ゆくゆくは大英帝国の門戸開放を狙っていた。 一方、対独主戦論者チャーチルは、米国の援助を得てドイツと戦うことで大英帝国を維持しようとした。 こうした背景で、「大英帝国の門戸開放・植民地解体」を狙うルーズベルトと、「大戦への巻き込み・最大限の援助獲得」を狙うチャーチルの駆け引きが始まった。 アングロサクソンの大戦略は、準備ができてない時は宥和で時間を稼ぎ、強敵に立ち向かうときは仲間を探して連合を組み、負けると分かれば仲間を見捨てて深手を避ける。 そうした戦略観から、両国は常に周辺の脅威や戦力バランスの変化を警戒する一方で、仲間としての意図と適性、支援義務の可否と限界、介入・支援能力を絶えず点検し、強敵やパートナーとの公式・非公式チャネルで意図の変化を探るのである。 (つづく)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||