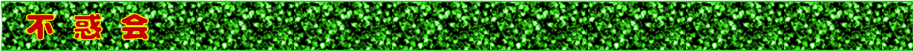
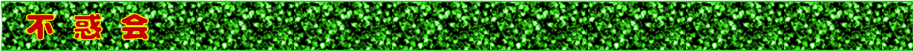
Falkland紛争における英・米・・・米国は如何に巻き込まれを避けたか? 本ケースの特徴は、①脅威―僻地の離島に奇襲侵攻を受けた事態、②対処―準備に時間の余裕がないまま奪回作戦を決断・決行した、③同盟―米国は紛争当事国の双方と同盟関係にあった、④結果―嫌がる大国を小国が限定的ながら巻き込みに成功した点にある。 日本にとって、「今そこにある危機」と言われる尖閣問題や、グレーゾーン事態に参考となるのではなかろうか。 (1) 小国の依存と反発 Falkland紛争(1982.4.2~6.14)は、アルゼンチンが近海の英国領諸島に奇襲侵攻したのに対し、英国は時間の余裕のないまま奪回作戦に米国を巻き込もうとした。 敢然と戦うことを選んだサッチャー首相は、チャーチルのように説得・交渉を行うためのチップも時間もない状況で、腰の定まらないレーガンの尻を叩き、イライラしていた。 だが、緊縮財政のため不人気だったサッチャー首相は、この紛争でのきわどい勝利から国民の圧倒的支持を受け、経済改革にも成功して英国の威信を一挙に回復させている。 二国間の同盟にあって、大国は小国の運命など歯牙にもかけない「非情」さや、小国の問題のみに拘束されるような誓約はしないとの「死角」がある。 また大国は、その力と威信と信頼を維持しようとし、常に地球的規模・見地から発想する。 だから大国は、同盟国間の矮小な領土紛争への巻き込まれを警戒し、現状維持のため小国に干渉し強圧をかける。 一方、危機に直面した小国は、大国の庇護に「依存」する一面と、自国のプライドや主権発揮から大国の統制に「反発」する一面があり、ジレンマが生ずることになる。 (2) 米国「領土紛争は局外中立」 Falkland諸島をめぐる英・アルゼンチンの主権交渉は150年余に及んだが、内政と経済に行き詰まったアルゼンチンの軍事政権は、国民の目をそらすため奇襲侵攻に踏み切った。 国防費の削減を進めていた英国は、領土交渉でも現状維持―租借の拒否と総督の派遣―をとり、アルゼンチンの暴発を予想しなかった。 軍事政権の強硬策は、尖閣諸島を「核心的利益」と位置付ける中国の暴発を暗示させる。 ア軍侵攻の兆候をつかんだ3月30日、米国は「いずれの側に立つか」について、ジレンマに陥った。 アルゼンチンとの間には米州機構に基づく相互援助条約があり、武器供与と引き換えに中南米での共産ゲリラ掃討を軍事政権に託していた。 一方で米国は、NATO条約の盟主として英国が侵略された場合、援助の義務を負っていた。 しかも、日米安保とは異なり自動介入である。 さらに当時の米国は、英国との間で「戦略核戦力の見直し」を進めており、米国製トライデント原潜の売却や、巡航ミサイルの英国配備について、米英の交渉は大詰めを迎えていた。 こうした背景で米国務省では、「米州大陸の安全・経済権益の直結」から南米諸国との関係を優先する国連大使と、「英国との特殊関係・核戦力の米ソ均衡」を優先する国務長官ヘイグ(NATO司令官の経歴)の意見が対立した。 やむなくレーガン大統領は、中立の立場から英・ア両国に武力の不行使・外交解決の調停を申し出た。 3月31日、レーガン大統領はアルゼンチンに作戦中止を説得したが、「米国には軍隊派遣の貸しがある」と考える軍事政権は、聞く耳を持たなかった。また、軍事政権トップが米国連大使と会談した際、Falkland諸島の奪回を匂わせたのに対し、「米国はちっぽけな領土紛争に介入しない」との言質を得ていた。 かつてモンデール駐日大使も、「尖閣諸島の防衛に日米安保は及ばない」と本音を漏らし、物議をかもした。 領土紛争に対する米国の基本は、自国が持つ利害関係のスケールの大きさと第三国間の紛争次元の低さから、原則的に「善意の第三者」に止まろうとする。 (3) レーガンのグズグスとサッチャーのイライラ 4月2日、アルゼンチンが奇襲侵攻し、Falkland諸島を占領して住民宣撫を開始した。 同島には英国系住民が3千人いたので、英国は艦隊による機動部隊の派遣準備を急いだ。 ヘイグ国務長官はロンドンに飛んで外交解決の説得にあたったが、サッチャー首相は「国際秩序の維持には侵略への抵抗こそ最も重要な原則で、米国は中立にこだわるべきでない」と突っぱねた。 次いでアルゼンチンを訪れたヘイグは、「英国は奪回作戦を真剣に考えており、そうなれば米国は英国を支持せざるを得なくなる」と、経済制裁の「脅し」を交えて説得に当たった。 だが軍事政権は、「住民宣撫に成功すれば、英国は上陸作戦を放棄する」と考え、経済制裁の中止と英機動部隊の派遣停止を、米国の説得に期待した。 占領による既成事実化と、機動部隊の出港準備の双方を睨んだサッチャーは、次第に米国の中立姿勢に苛立ちを見せた。 そして再訪したヘイグに対し、核戦略問題で米国に妥協した実績や、イランにおける米国大使館人質事件(1974年)での支援を挙げ、「米国には貸がある」と主張し、英国支持を鮮明にするよう迫った。 その際、1万3千kmに及ぶ遠征作戦の遂行と、奇襲受けで兵站準備が整っていない点を強調し、米軍による兵站支援、米空軍基地の一時的借用、NATO用備蓄弾薬の取り崩し、諸島占拠中のアルゼンチン軍の情報提供について、米軍の協力・支援を要請した。 (4) 英国の依存vs 米国のアメとムチ 4月下旬、英国は機動艦隊を逐次出航させたが、長大な距離から現地への到着は遅れた。 この間、米国務省では「いずれの側に立つか」論が再燃した。 そこで大統領補佐官が調整し、「しばらくは成り行きを見守る」として中立的態度を継続することにした。 ところが、米国世論の間には「国際秩序の維持」という正義論から、「英国側に与すべき」との意見が高まった。 これはサッチャー首相が「将兵の血をもってでも領土を奪回する」と国連で演説し、機動部隊を出航させたことや、米国民が「国際正義にとって武力行使は不可欠」と認識したことを、マスコミが書き立てた影響が大きい。 「血の代償は英軍が支払うのであり、米軍は直接介入しない。ならば、友邦の自助努力には援助の手を差し伸べるべし」という国民感情が根底にあった。 もちろん英国は、対米宣伝活動と米国議員に対するロビー活動を米国内で強力に展開していた。 こうした情勢で4月30日、英国はFalkland諸島周辺海域の封鎖を発表した。 武力行使の宣言である。 レーガンは政策を転換し「英国に軍事支援を与え、アルゼンチンには経済制裁を加える・・・武力侵略は断じて成功に終わらせてならない」と声明した。 国民の支持を失いかねないと見たレーガンは、間接支援に舵を切ったのである。 これを契機に、英本土とFalkland諸島の中間に位置するアセッション島に英軍機動部隊の兵站・空軍基地が設けられ、米軍による支援・協力が始まった。 日中間の尖閣紛争を想定するなら、アセッション島は嘉手納飛行場、那覇軍港施設に相当するだろう。 Falkland諸島奪回のため英国は、軽空母2隻、巡洋艦等29隻、上陸強襲艦4隻、原潜4隻、民間徴用船50隻余、戦闘機40機余、ヘリ46機、最終的に5万人を送り込んだ。 諸島はアルゼンチンに近く、航空優勢を奪回するため軽空母と戦闘機を送り込んでいる。 また季節は冬に向かっており、膨大な燃料・弾薬・ミサイル・食糧・衣類・消耗品が必要だった。 しかし米国政府は、基地や補給品を提供する代償として、英軍の奪回作戦に干渉した。 英軍の戦闘地域をFalkland諸島周辺にとどめさせ、アルゼンチン本土への爆撃を認めなかった。 また、作戦の長期化を嫌って衛星情報を英国に提供し、英軍の上陸・奪回作戦を支援した。 一方でアルゼンチンには、英軍による本土爆撃が起らないと保証し、停戦後の対英交渉での仲介(有利に働きかける)を約束していた。 (5) 英国の感謝と不満VS 米国の同盟修復 6月中旬、英国の奪回作戦は成功して終結した。 局地紛争の仲介に関する米国の「戦争と平和の哲学」は、紛争が過熱・暴走・長期化して世界の平和と大国の利益を脅かしてはならないというものである。 そのため、初期段階では中立の立場から調停にあたり、それが失敗すれば紛争当事者の軍事的疲弊や、一応の軍事結節・決着を見守り、その段階で講和の仲介・強制に乗り出す。 こうした「紛争不介入の原則」は、第4次中東戦争におけるキッシンジャー外交を受け継いだものである。 1980年代のレーガンとサッチャーは、保守的な原則を頑固に主張して改革を進める点で共通しており、個人的にも親密な関係を築いていた。だが、危機における主権の本質が「自己決定権」とするなら、紛争の舞台裏でレーガンは、武力行使・作戦区域の範囲、武力手段の選択、終結の時期・要領等に干渉し、停戦後も占領地撤退、捕虜交換、見せかけの平和回復を強制するなど、サッチャーにとっては厄介な盟友だったといえよう。 しかしながら、国連における非難決議や制裁決議が出されば拒否権を発動する構えを示し、武力行使の本格化や長期化に伴って物的戦力を補填する米国の政治・軍事・経済支援は、英国にとって死活的重みをもっていた。 それゆえサッチャーは米国に対し、「対立・反発」を繰り返しつつも、最後は「協調・妥協」することで、国益と正義の追求に邁進できたのである。 こうした「英国のしたたかさ」は、危機における同盟協議の手本になろう。 嫌がる米国を牽制・拘束した要因は、 ①米国の対ソ核戦略を先取りした補完・協力関係を平時から確立していた。 ②主権回復にあたる機動部隊の派遣を躊躇せず、その実行を対米交渉のカードとした。 ③領土主権の回復を目指す武力行使に国民の団結力を結集させたサッチャーの能力。 ④米国が持つ同盟政策の矛盾に対する揺さぶりと、NATO諸国を活用した対米圧力。 ⑤米国に関する正確な政治・軍事情報の収集・分析と活用しうる能力の保有。 それらを総合し、米国政府の移ろいやすい利害関係(米州政策・対ソ戦略・孤立主義)や、米国民の正義観に訴え、「山(米国指導者と世論)を動かした」のである。 湾岸戦争におけるイスラエル・米国・・・小国が如何に大国を振り回したか? 本ケースの特徴は、①脅威―「もらい事故」的な波及事態、②対処―小国側に自己救済能力がありながら制限を受けた、③同盟―防衛の約束はあるが共同対処の基盤はない、④結果―小国が大国を振り回したものの、米国の拡大抑止を引き出す結果となった点にある。 (1) 小国の抑止戦略破綻 イスラエルと米国も「特殊関係」と言われている。 数次にわたる中東戦争でのイスラエル勝利の裏には、米国の軍事的支援と政治的後押しがあった。 しかし、両国間に同盟条約はないし、常設の協議機関もない。 歴代大統領は、中東政策の一つに「イスラエルの生存と安全」を掲げ、当選した暁に同国を訪問して声明するのを慣例としていた。 だがこの湾岸危機・戦争を通じ、「核を含む大量破壊兵器使用の恫喝・警告」という外交カードが用いられ、それによって米国が小国イスラエルに振り回される結果を招いた。 周辺を核保有国に囲まれた日本としても、米国による「核の傘」の信頼性を確保する必要があるし、核恫喝に対抗する日本独自の手段が欠かせない。 イラク軍がクウェートに侵攻した1990年8月、米国は衝撃的を受けたが、イスラエルは脅威の波及を予想しなかった。 「アラブ諸国に対する抑止戦略が破られることはない」とタカをくくっていた。それは、①「矛」として各種の核弾頭・ミサイル・戦闘機を備え、②「侵略には先制攻撃も辞さない」と警告しておき、③1982年のイラク原子炉に対する奇襲爆撃を思い起こさせれば、サダム・フセインが手出しすることはないと考えていた。 ところがサダムは、危機を「アラブ対欧米諸国」に発展させるため、イスラエルへの化学攻撃の恫喝を繰り返し、弾道ミサイルを国境近傍に展開した。 これを知ったイスラエル政府や国民は、抑止戦略が破綻しており、ユダヤ民族の抹殺を狙う暴挙だと騒ぎ始めた。 イスラエル国民は「イラクのミサイルを直ちに叩け」「さもなくば抑止戦略が腐食する」と叫び、即時の先制攻撃・爆撃の発動を政府に要求した。 イスラエル国防相が直ちに米国に飛び、先制爆撃への協力を求めたのに対し、ブッシュ政権は「アラブ諸国の多国籍軍への参加意欲を乱すべきでない」と反対し、イスラエルの望む協力を拒否した。 さらに、アラブ諸国の結束を高める措置として、彼らへの武器売却や軍事援助を増やしていた。 (2) 米国への反発・「核カード」 米国との間で先制爆撃の協議が進展せず、アラブ諸国の軍備が強化される状況で、イスラエル国民の間に苛立ちと焦燥が募った。 一旦取得した「既得権益―アラブを上回る軍事援助」の停止は、小国の指導者や国民にとって「米国の国益優先」「理不尽な圧力」と映り、被害者意識の高まりやアラブとの密約・陰謀説を募らせる。 秋になり、アラブ諸国の多国籍軍参加が固まったが、サダムは「エルサレム解放」を煽り続け、「化学兵器使用の恫喝」「石油戦略」で欧米・イスラエルに挑戦する姿勢を崩さなかった。その結果米国は、イラクに対し「経済制裁か、武力解決か」、イスラエルに対し「先制攻撃に自制を求めるか、協力に転換するか」のジレンマに陥った。 というのも、米国はイスラエルから「イラクの国家機密・秘密宮殿等に関する戦略情報」を得ていた。 そこで同国の協力を継続して受ける報償として、「盾」であるミサイル防衛強化手段―最新式迎撃ミサイル・PC2(ペトリオット)―供与を決定した。 そしてこれが、イスラエルの先制攻撃を阻止する決め手になると考え、「矛」の使用―先制攻撃―は認めなかった。 ところが、自力救済の能力がありながらそれを封じられたイスラエルは、「主権の侵害・民族の危機」と見て、米国に対し「核カード」を用い始めた。 政府高官や軍トップが、「化学攻撃に対する報復は大規模なものになる」「強力な手段で報復する」と繰り返し発言した。 核使用の警告である。 こうした「核カード」は、1973年の第4次中東戦争で用いられた。 キッシンジャーが戦争を短期間で終わらせようとし、武器・軍需品の補給差し止めを強行したのに反発し、カードを切った。 もともとイスラエルの核保有は、最悪事態に陥った場合の軍事的使用と、庇護国である米国に支援を強要する手段としての目的だった。 事実、1986年に政府は、世論調査で「核兵器使用の是非」を問うている。 この時、「賛成」意見が36%であった。 だがこの数値は、88年に53%に上昇し、湾岸戦争が始まった91年1月には88%に跳ね上がった。 こうなると米国としては、「核使用の敷居は低い」とみなさざるを得ない。 「中東における核・化学兵器の拡散防止」を掲げるブッシュ政権としては、「イスラエルの先制攻撃・核使用の阻止」「イラクのミサイル攻撃阻止」「多国籍軍の団結・勝利」という難しい問題の解決・検討に入った。 一方で、米国ユダヤ人協会やユダヤ・ロビーは米国議会に働きかけ、イラクの化学攻撃を抑止するための「先制攻撃の正当性」を訴え続けていた。 中間選挙を控えたブッシュは、「戦略的お荷物」の扱いに悩まされていた。 (3) 米国の「拡大抑止」発動 11月の中間選挙で勝利を得たブッシュ大統領は、イラクに対しては断固とした武力解決、イスラエルに対しては「先制攻撃も核使用も認めない」方針を固めた。 措置の第一は、イラクに対する拡大抑止の発動である。 ブッシュ大統領はベーカー国務長官をスイスに派遣し、イラク外相との会談で「イラクがイスラエルを化学兵器で攻撃すれば、米国はそれを米国に対する攻撃とみなし、大量破壊兵器の使用も辞さない」と警告させた。 「米国に対する攻撃」を作為するため、米国はイスラエル国土に米軍将兵を派遣し、彼らを人質とすることで「多様な報復手段」を警告し、イラクとイスラエル双方の暴走を封じ込めようとしたのである。 措置の第二は、イスラエルに対して共同防衛を提示し、それにより先制攻撃の放棄を迫った。 過去の数次にわたる中東戦争で、米軍部隊・戦闘機がイスラエル国土で任務に就いた例はない。 シナイ半島に空挺師団を停戦監視目的で緊急投入した例はある。 多国籍軍の攻撃開始が迫る1月上旬、ブッシュ政権は国務副長官等をイスラエルに派遣し、ミサイル防衛に「米軍参戦の共同対処」をとらせ、「被害を受けた場合は金銭補償する」ことで、イスラエルに「先制・報復攻撃の放棄」を迫った。 だがイスラエルは、「先制攻撃は控えるが、報復攻撃は将来の安全保障の見地から欠かせない」と突っぱねた。 米国の対応を、「主権の制約」「従属関係の強要」と見たのである。 イスラエルにとって「主権」とは、危機の際にも自己決定能力を保持することであり、その制限は民族の威信、プライドに瑕がつくだけでなく安全が損なわれる。 「報復攻撃」こそがイラクの化学攻撃を抑制する切り札だと主張し、制約なき主権行使に固執した。 (4) 大国の共同介入とリスク引受け 多国籍軍が爆撃開始に踏み切った翌日深夜、イラクは10発の「通常弾」をイスラエル都市に撃ち込み、7人の男女が負傷し、多くの建物が損壊した。 イスラエル政府・国民は、米国供与のPC2が役に立たないこと、多国籍軍による「ミサイル狩り」が不調だったことにショックを受け、結果的には「イラクによる化学兵器使用の恐怖が現実になった」と、パニックに陥った。 イスラエル国防相は米国防長官に、戦闘機による報復爆撃の支援・協力を求めた。 これに対し米国側は、①「ミサイル狩り」作戦の最大限の強化、②ミサイル迎撃における米軍共同対処部隊・器材の増加、③敵ミサイルの発射に関する早期警報の提供、④被害者に対する経済補償の確行を約束した。 それでもイラクのミサイル攻撃が続いたことから、今度はイスラエルが「報復か自制か」のジレンマに陥った。 報復作戦の実施には米軍の飛行支援と、目標情報が不可欠である。 更に、それを実施してもミサイル攻撃を完全に阻止しうる保証はない。 それどころか、化学攻撃のリスクが一層高まる。 こうした状況でイスラエル政府は、「報復か自制か」の世論調査を行った。 しかし、通常弾のミサイルによる人的被害は限定的であり、報復すれば化学弾の使用を誘発しかねない。 結局良識派の「化学弾が用いられない限り、自制を続ける」意見が多数を占めた。 こうしたことから政府は、①ミサイル迎撃に関しては米軍との共同対処でリスクを分かち合い、②報復作戦に関しては自制を継続して様子を見る、③しかし化学兵器が用いられれば躊躇なく報復する、との「米国との共同防衛」「段階的報復論」に転換した。 結局、戦争終結まで、サダムは化学兵器を用いなかったし、イスラエルも報復攻撃を自制し続けた。 停戦後の国連調査で、イラクが化学弾頭30発を保有していた事実が確認されている。 またサダムは、「化学攻撃に対するイスラエル・米国の核報復は『ありうる』と判断していた」と報告された。 (5) 大国とのバーゲニング・パワー イスラエル国民は米国が採った措置、①米国への攻撃とみなされるべく米軍部隊をイスラエル国土に人質としたこと、②多国籍軍が「ミサイル狩り」に最大限の努力をしたこと、③早期警戒情報を迅速に提供して国民の生命財産保護に貢献したことに、深く感銘した。 但し、共同防衛によるミサイル迎撃の効果は、ほとんどなかった。 それでも、イスラエル国民の米国に対するイメージは一転し、「信頼と感謝」へ変化したのである(世論調査の結果から)。 イスラエル国民が米国との共同対処に満足したのは、共通の敵や利益に関する認識が大国と小国間で一致したというより、少数民族の存続が大国将兵の人質と「拡大抑止」によって守られたとの認識による。 WWⅡではどの国も手を貸してくれず、ホロコースト・民族抹殺の危機に陥ったという民族的恨みの逆バネ現象から、一国主義を捨てて対米協調に向かうことになった。 イスラエルが対米関係で見せた「したたかさー大国を振り回す」は、何から生まれたか。 ① 国の政戦略を先取りした補完・依存(戦略情報の提供)関係の確立。 ② 主権を維持する手段を放棄せず、米国と交渉する際のカードとした。 ③ 国に対する反発や不信感、一方で生存や安全に関する国民の知恵と執念。 ④ 大国が持つ政策の矛盾に対する揺さぶりや、小国に協力的な相手国内集団の活用。 ⑤ 国に関する正確な政治・軍事情報の収集と、それを活用しうる能力。 ⑥ 国の移ろいやすい利害関係や、国民の関心を読み取る政治システム ではなかろうか。 国際政治上のパワーとは、「紛争状態にあるとき、相手の抵抗を排除しても自己の能力を相手に押し付ける能力、意思を押し付ける相手に抵抗してその要求を無効にする能力」だと、永井要之助は『時間の政治学』で述べている。 湾岸危機・戦争の舞台裏でこのパワーは、「イスラエルの核カード」「米国の拡大抑止」を引き出すすさまじさを見せた。 原因は、同盟関係に付随する猜疑心や焦燥感であり、ぎりぎりの主権や生存が試された結果である。 これまで我が国は「核の傘」「非核三原則」を堅持し、議論すら封じてきた。 だが北の核が用いられた場合、米国が核報復を行うかどうかわからない。 冷戦終結から24年、確証破壊の理論は封印され、大国による核使用の敷居は高まっている。 現在の国際社会で、実際に核を使うことは、同盟義務だとしても、非難される可能性は高い。 オバマ大統領は、「長期的には核兵器を廃絶すべき」と宣言している。 そこで無人機の使用や、他の大量破壊兵器の使用を警告するのかもしれない。 ブッシュ・ベーカーコンビはそうした。 しかしキッシンジャーは、アジアの核バランスが不安定であり、「いずれ日本も核武装する」と述べている。 核には核でなければ絶対的効果はない。 日本の「タカ派的核保有論」「ハト派的核廃絶論」はともに非現実的選択である。 そこで、「核の傘」を「補強」する意味から「核開発の曖昧政策」を提唱したい。 核兵器を作る技術能力を持つ日本は、「核を持てるのに持たない」政策を採り続け、非核保有国の中でリーダーシップを発揮する一方で、米国に核拡散防止努力の推進と、万一の場合の拡大抑止の確行について圧力をかける方が、むしろ現実的なのではなかろうか。 おわりに (1)危機における同盟の拘束 大国を巻き込むための条件・要因は、次のようにまとめられる。 ①条約の有無や介入の実績 ②作戦のための共同機関とその運営 ③介入を正当化する危機の形態・大義 ④大国側軍隊の能力と余裕 ⑤大国側国民の介入同意・支持 ⑥リスク・コストに対する見返り ⑦介入の効果や勝利の見通し ⑦ 導者同士の信頼関係 さて、3・11の「トモダチ作戦」で米国は、次の3点を明確にした。 ①日本の指揮統制システムへの疑念。②介入にあたっての審査と条件。③ギブ&テイクの原則である。 ①日本の指揮システム。 大統領をはじめ米国指導者は、日本政府の対応がトップダウンでなく、リーダーシップが見えず、指揮統制が機能不全だった点に不安といら立ちを募らせた。 日本版NCSの運用が始まり、常設の事務局に将補の自衛官が加わったので、システムの改善は期待できる。 但し、日米同盟における問題は、常設の共同機構や多重委員会による相互拘束が計られていない点にある。 共同機構の設置は、一方が戦略的利益を得たとしても、それが他方の安全を脅かさない保証となり、連合が猜疑心の温床になることを回避しうる。 米国を欧州に縛りつけようとするNATOは、そうした相互拘束を活用している。 ②介入の審査。 米国は放射能漏れ対処のため各種の支援や措置を申し出たが、米軍人の現場投入は明確に拒否した。 日本側の身を切る行動がない限り、米兵の血を流すわけにはいかないとの原則で、それが陸自ヘリによる原子炉への散水につながった。 深刻な危機が予想される場合、条約の有無にかかわらず大国は、介入判断にあたり小国の能力を審査する。 大戦初期の米国は、Battle of Britainを戦い抜いた英国に、また困難を克服してドイツを阻止したソ連に、大量の武器を与えている。 反対に、自助努力を欠いた泥縄準備と敗北主義から、米国にリスクとコストを求めた仏国を、冷たく突き放した。 ③ギブ&テイク。 国内に多くの原発を持ち、原子力推進機関を保有する米国は、原発事故に関するノウハウや情報収集に強い意欲を示し、支援によるリスクやコストの見返りとして情報提供を求めた。 裏返せば、日本にとって「介入を促進する・介入を強要するカード」が必要ということである。 米国指導者や国民は、同盟関係においてもギブ&テイクこそがフェアーと考える。 したがって、大国と小国がリスクを分かち合うことがフェアーと考え、一方的に助けることに納得しない。 そのためには、コストやリスクを目に見える形で分かち合う「介入促進カード」が欠かせない。 同盟の固さは、技術・情報等の提供による多角的な相互依存、重畳的な協力関係が意味を持つからである。 一方で、国益・主権・生存には譲れない一線が必ずある。 例えば、大東亜戦争終末期における「国体の護持」である。 そこで、同盟国に対しても「介入強要」カードは欠かせない。 米国が嫌がるカードとしては、「溜めこんだ米国債券の大量売却」とか、「核開発を検討する」との方針転換が挙げられる。 核兵器の開発技術は日本も持っており(『偕行』7月号中川論文)、「できるが、それを自制している」と言うのも対米カードになる。 (2)したたかな米国と付き合うため 米国の同盟政策を中長期的な観点から振り返って見ると、柔軟、現実的、見方によってはご都合主義的とも見えるダイナミックな変化を見せてきた。 WWⅡ前まで同盟の経験を持たなかった米国にとって、「対等」を主張する小国との同盟はしっくりいかない。 米国政権が国益を優先して切り捨てた例に、蒋介石政府、南ベトナム、パーレビ―政権(イラン)がある。 イデオロギーと拡張主義で天敵と見ていた旧ソ連とも、あっという間に提携した。 PKОも米国の利益にならない場合は一切関与しないし、米州大陸・諸国への関与は特殊権益を主張して拒否する。 新興国の核開発についても、イスラエル・インド等の核装備には鷹揚だったが、北朝鮮・イラン等に対しては不寛容で、二重基準を使い分ける。 米国の指導者・学者・官僚は、衰えたといえども世界の警察官としてのプライドを持っている。 また、アングロサクソン的観念で同盟をギブ&テイク、互恵主義こそフェアーと考える。 したがって小国との関係においても、「機会の平等」を優先し、「結果の平等」について気にしない。 むしろ自分たちは優れているという気概の下で、「国際秩序の維持」「人権」「民主主義」押しつける。 以上の因って来たるゆえんは、その時々の米国益の最優先と政権の維持・世論の動向にある。 軍事力、経済力、政治力の卓越を背景に、危機においては自国の利益を害する国を容赦せず、核大国であるロシアや中国を除き、いつでも鉄槌を下せる構えも垣間見える。 小国側にとっての米国は、頑固で、自意識が強く、結果の平等を求める押しつけや「国益優先」は、許しがたいと映ってきた。 日本だけでなく、英国もイスラエルもそれで苦労してきた。 こうした米国の特徴は、「神に対してのみ忠実であれば、世俗には何をしても許されるとの精神に起因する」と見る説もある。 だがそれはともかく、かかる認識ギャップと歴史的事実を認識したうえで、日本人は同盟・分担・妥協について考えねばなるまい。 米国軍人の中佐以下は気さくでいいやつが多い。 だが、国際政治や危機にあってはウエットな「情緒や感情」が入る余地はない。 世界の警察官としてのオバマ政権の介入意図は落ちているが、米軍の能力―戦略開発・情報・装備・態勢・兵站・即応等―の抜きん出た状況は、中期的に続く。 それを軽視するわけにいかない。 したがって、米国のしたたかさを認識しつつ、我が国の主権と安全を確保するには、「尖閣に安保を適用してもらいたい」との懇願から脱却し、小規模・グレーゾーン事態での「自主防衛態勢」の確立を図る一方で、東アジアの安定を図る戦略提言を行うことだ。 それが「積極的平和主義」の本旨であり、彼らの言うフェアーであり、自助努力の象徴になる。 そのためにまず、安保条約第4条に基づいて制服を含めた常設の協議機関を新設し、認識ギャップを埋める努力を続けることだ。 それが、日米同盟にスキを与えない結果を生むことにつながるだろう。 参考とした資料等については、次の論文を参照されたい。 ①フランス関係。「第二次大戦前における仏国の国防政策」陸戦研究・平成19年6月号。 ②イギリス関係。「第二次大戦初期における英国の国土防衛」陸戦研究・平成19年1月号。 ③アメリカ関係。「第二次大戦前における米国の参戦準備」陸戦研究・平成19年7月号。 ④Falkland紛争。「離島防衛における危機管理」陸戦研究・平成14年4月号。 ⑤湾岸戦争。「湾岸戦争における米国・イスラエル同盟」陸戦研究・平成11年7・8月号。(2014.06.13)
|
||||

喜田 邦彦
6 区 隊 職種:普通科