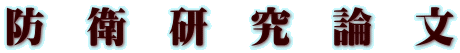| 俁丂忣惃敾抐乗庡娤傪攔偟嵟埆傪梊憐偣傛 丂偙偺暣憟偼偺偪偵乽婲偒側偔偰傕傛偐偭偨暣憟乿乽梷巭偵幐攕偟丄婏廝傪庴偗偨暣憟乿偲屇偽傟偰偄傞丅僒僢僠儍乕庱憡偵乽傾儖僛儞僠儞孯偺忋棨嬤偟乿偑揱偊傜傟偨偺偼丄怤峌偺俆擔慜偱偁傞丅婏廝傪庴偗偨嵟戝偺尨場偼丄忣惃敾抐偺儈僗偱偁傝丄梷巭懳墳傪庢傜側偐偭偨偙偲偵傛傞丅壓堾偱偦傟傪捛媦偝傟偨僒僢僠儍乕偼丄乽怤峌慜抜奒偵偍偗傞惌晎偺愑擟偲慬抲乿偵娭偡傞亀僼儔儞僋僗挷嵏埾堳夛亁傪愝抲偡傞帠懺偵捛偄崬傑傟偨丅挷嵏埾堳夛偵偍偄偰奜柋徣偼丄乽俁寧29擔傑偱偼丄孯帠惌尃懁偵怤峌堄恾偼側偐偭偨丅偟偨偑偭偰怤峌忣曬傪擖庤偱偒傞偼偢偑側偄乿偲庡挘偟丄敾抐儈僗傪擣傔側偐偭偨丅偩偑偦偆側傞偲丄傾儖僛儞僠儞偼怤峌堄恾傪妋棫偟偰傢偢偐48帪偱弌悆弨旛傪惍偊丄彨暫傪孯娡偵搵嵹偟丄僼僅搰偵岦偐偭偨偙偲偵側傝丄暔棟揑偵晄壜擻偱偁傞丅奜柋徣偼憗偄抜奒偱堄恾傪偮偐傫偱偄偨偺偱偁傝丄忣曬昡壙傪岆偭偨丒忣曬憖嶌偝傟偨偙偲偼傑偪偑偄側偄丅 仠怤峌侾擭俁偐寧慜(1981擭弶摢) 丂奜柋徣偺忣惃敾抐偼丄傾儖僛儞僠儞偑峴摦傪婲偙偡壜擻惈偼斲掕偱偒側偄傕偺偺丄怤峌偼嵟屻偺愗傝嶥偲偟偰壏懚偟丄嘆崙楢偱偺峈媍怽偟擖傟仺嘇僼僅搰偵懳偡傞宱嵪晻嵔仺嘊嬤奀偱偺帵埿峴摦仺嘋撿僕儑乕僕傾搰偺愯椞偲丄岠壥傪柸枾偵寁嶼偟側偑傜抜奒揑偵埑椡傪壛偊偰偔傞偲傒偰偄偨丅 偟偐偟僽僄僲僗傾僀儗僗偺塸崙戝巊娰偼丄乽孯帠惌尃偑嫮峝嶔傪偲傞壜擻惈偼崅偄丅摿偵僞僇攈偺奀憡偼僼僅搰扗夞偺栰朷傪書偄偰偄傞乿偲丄杮徣偵寈崘偟偰偄偨丅 仠怤峌俁偐寧慜(1982擭1寧) 丂傾儖僛儞僠儞偑岎徛嵞奐傪梫媮偟偨偑丄堷偒怢偽偟傪恾傞塸奜柋徣偼愊嬌揑斀墳傪帵偝側偐偭偨丅梫媮傪潧偹偮偗傜傟偨孯帠惌尃偑丄懺搙傪偑傜傝偲曄偊偨偺偼偙偺帪揰偱丄傾儖僛儞僠儞崅姱偑暷崙偵嫮峝庤抜傪傎偺傔偐偟巒傔偨丅 仠怤峌侾偐寧慜 丂傾儖僛儞僠儞偼塸崙偺岎徛懺搙傪嫮偔旕擄偡傞僐儈儏僯働傪敪昞偟丄怴暦偑栆楏側斀塸僉儍儞儁乕儞傪奐巒偟偨丅尰抧偺塸戝巊娰偼丄乽孯帠惌尃偑嫮峝嶔傪偲傞壜擻惈偑崅偄乿偲杮崙偵曬崘偟偨偑丄杮徣偼偦傟傪乽僆僆僇儈彮擭乿偩偲庴偗巭傔偨丅僒僢僠儍乕庱憡偼乽梷巭慬抲傪峫偊傞傋偒偱偼乿偲奜憡偵姪崘偟偨偑丄1977擭偺娡掵攈尛偺椺傪専摙偟偨奜憡偼乽尨愽攈尛偼岎徛傪攋抅偝偣傞乿偲曬崘偟偰尒憲偭偨丅尨愽偺僼僅乕僋儔儞僪摓拝偵偼俀廡娫傪梫偡傞偺偱丄偙偺帪揰偱偙偺梷巭慬抲偑偲傜傟偰偄傟偽丄暣憟偼夞旔弌棃偨偲尵傢傟偰偄傞丅屻偵壓堾偱偙傟偑栤戣偵側偭偨丅 仠怤峌俀廡娫慜 丂傾儖僛儞僠儞偺孄揝夞廂嬈幰偑奀孯偺曗媼娡偱撿僕儑乕僕傾搰偵忋棨偟丄塸崙偺斀墳傪扵偭偨丅偩偑塸奜柋徣偼丄偦傟傜偵懳偟恆巑揑側峈媍偼峴偭偨傕偺偺丄帠懺偑敪揥偟偨応崌偺曬暅峴摦偵偮偄偰偼堦愗寈崘偟側偐偭偨丅 仠怤峌10擔慜 丂僽僄僲僗傾僀儗僗挀嵼偺塸崙忣曬婡娭偑丄乽奀孯偺戝婯柾墘廗偼僼僅彅搰怤峌偺慜怗傟乿偲偟偰丄怤峌偼係寧忋弡偲儘儞僪儞偵曬崘偟偨丅偩偑儘乕僨僔傾栤戣傪書偊傞惌晎偼丄偦傟傪儅僀僫乕偩偲傒側偟丄亀奀奜丒崙杊埾堳夛亁偵曬崘偟側偐偭偨丅 仠怤峌侾廡娫慜 丂傾儖僛儞僠儞孯偵傛傞撿僕儑乕僕傾搰忋棨偺僯儏乕僗偑儘儞僪儞偵揮憲偝傟偨丄偟偐偟惓婯偺儖乕僩偵偼忔傜偢丄庱憡偵偼撏偐側偐偭偨丅崙杊憡偼丄嬞媫懳張寁夋偺廋惓偲強梫宱旓偺擯弌偵偮偄偰丄亀崙杊丒奀奜埾堳夛亁偱嫤媍偡傋偒偩偲恑尵偟偨偑丄奜柋徣偼乽傾儖僛儞僠儞奀孯偵僞僇攈儉乕僪偼崅傑偭偰偄傞傕偺偺丄惌晎慡懱偵怤峌偺堄恾偼尒偊側偄乿偲斲掕偟偨丅 仠怤峌俆擔慜 丂摑崌忣曬埾堳夛偼乽傾儖僛儞僠儞偑怤峌嶌愴傪峫偊偰偄傞柾條乿偲丄偦傟傑偱偺昡壙傪戝偒偔廋惓偟偨丅傾儖僛儞僠儞奀孯偺捠怣朤庴偵惉岟偟丄懕乆偲僼僅搰怤峌傪偆偐偑傢偣傞忣曬偑撏偒丄妋擣偑庢傟偨偲偄偆傢偗偱偁傞丅偙偺帪揰偱尨巕椡愽悈娡偺攈尛偑寛掕偝傟偨偑丄乽怤峌偡傟偽晲椡偱曬暅偡傞乿偲偺寈崘傕偟側偄傑傑丄僒僢僠儍乕偼婏廝帠懺偵撍慠曻傝崬傑傟丄堦婥偵懳張峴摦傪寛堄偟偨偺偱偁傞丅 仠怤峌俁擔慜 丂傾儖僛儞僠儞嬻曣偺曽岦曄姺偐傜丄塸崙杊憡偼僼僅搰傊偺怤峌傪妋怣偟丄庱憡姱揁偵媫曬偡傞堦曽偱丄婡摦晹戉偺攈尛偵岦偗偰弨旛傪奐巒偟丄崙杊徣撪偵嶌愴杮晹傪奐愝偟偨丅偟偐偟塸奜柋徣偼丄僂儖僌傽僀偲偺崌摨墘廗偲偺尒曽傪幪偰側偐偭偨丅 仠怤峌俀擔慜 丂塸崙偼儗乕僈儞暷崙戝摑椞偵揹曬傪懪偪丄乽僈儖僠僃儕戝摑椞偵怤峌傪巭傔傞傋偔捈愙榖傪偟偰偔傟側偄偐乿偲棅傒崬傫偩丅偟偐偟乽怤峌偡傞側傜晲椡偱曬暅偡傞乿偲偺寈崘偼敪偟偰偍傜偢丄枹偩奜岎岺嶌偵幉懌傪抲偄偰偄偨丅枩堦傪憐掕偡傞崙杊憡偼丄僼僅乕僋儔儞僪憤撀偵懳偟乽傾儖僛儞僠儞愽悈娡偺愙嬤乿傪寈崘偟偨丅 仠怤峌慜擔俋帪30暘 丂塸奜柋師姱偑乽傾儖僛儞僠儞偑柧擔丄怤峌偡傞柾條乿偲庱憡偵曬崘丅庱憡偼丄僼僅乕僋儔儞僪憤撀傊偺嬞媫楢棈傪巜帵丅尰抧偵偄偨79柤偺奀暫戉堳偼丄婡枾彂椶偺從媝偲墳媫抸忛摍偺丄偁傢偨偩偟偄弨旛傪奐巒偟偨丅 仠怤峌摉擔(係寧俀擔)俀帪15暘 丂儗乕僈儞戝摑椞偐傜乽僈儖僠僃儕偼嶌愴拞巭傪嫅斲偟丄怤峌寛堄傪屌傔偰偄傞乿偲偺揹曬偑撏偄偨丅奜岎岺嶌偑愨偨傟偨弖娫偱偁傞丅屵慜係帪15暘丄尰抧憤撀偼搰柉偵懳偟旕忢帠懺傪愰尵丅屵慜俋帪25暘丄憤撀偼枩嶔恠偒偰庣旛戉偵崀暁傪柦椷丅屵屻俈帪敿丄椪帪妕媍偐奐偐傟丄婡摦晹戉偺弌峘傪寛掕偟偨丅 丂寢嬊丄乽婏廝傪庴偗偨孅怞乿偲乽忣曬昡壙儈僗乿偺愑擟偐傜俆擔偵僉儍儕儞僩儞奜憡偑帿擟偟丄乽傾儖僛儞僠儞偺怤峌堄恾偺嶡抦乿傗乽懳墳慬抲偺抶傟乿偲偄偆惌晎偺晄庤嵺偺捛媦偑亀僼儔儞僋僗挷嵏埾堳夛亁偱巒傑偭偨丅擭枛偵採弌偝傟偨曬崘偱偼丄乽怤峌嶌愴偼1981擭12寧丄奀丒棨孯僩僢僾偵傛偭偰寛掕偝傟偨偨傔丄堄恾偺嶡抦偼崲擄偩偭偨丒丒丒怤峌偼梊憐傕弌棃側偗傟偽丄梊杊傕弌棃側偐偭偨乿偲寢榑偯偗傜傟偰偄偨丅偙傟偵懳偟媍夛傗儅僗僐儈偼丄乽恎撪乮惌晎乯偺愑擟捛媮偵娒偄乿乽惌晎偑廫暘側懳墳嶔傪偲偭偰偄傟偽丄婏廝偼旔偗傜傟偨偼偢偩乿偲偍偝傑傜側偐偭偨丅擔杮偱傕丄拞崙嫏慏懱摉偨傝帠審傪愬扟挿姱偑庢傝巇愗傝丄埨慡曐忈夛媍偵偐偗傞偙偲傕丄妕媍偵帎傞偙偲傕側偔丄庱憡偺奜梀拞偵張棟傪寛掕偟偨丅嶲堾偺栤愑寛媍偼摉慠偱偁傞丅 丂峏偵塸崙偱偼丄乽尰抧戝巊娰偺寈崘偑側偤惗偐偝傟側偐偭偨偐乿偲偄偆揰偑栤戣偵側偭偨丅尨場偺戞堦偼丄奀奜忣曬傪堦尦揑偵昡壙偡傞憤崌忣曬埾堳夛偑丄忣曬検偺懡偝偲桪愭弴埵偵娭偡傞岆敾抐偐傜丄傾儖僛儞僠儞忣曬傪廳帇偟側偐偭偨揰偱偁傞丅忣曬偺堦尦壔傗慻怐偺摑崌壔偼岠棪揑偵尒偊傞偑丄昡壙偺僠僃僢僋偑娒偔側傝丄巚峫偺暆偑嫹偔側傞媡偵丄擔杮偺応崌偼徣挕偛偲偵忣曬妶摦偑峴傢傟丄偄偞偲偄偆偲偒乽偲偭偰偍偒偺忣曬乿傪帩偪弌偟丄懚嵼堄媊傪嫞偄偁偆丅偙傟偼丄忣曬偺岠棪揑側廂廤丒暘愅丒昡壙偲偄偆尨懃偐傜偡傞偲桳奞偩偑丄嫞偄崌偄偱忣曬偺幙偑忋偑傞偲偄偆儊儕僢僩偼偁傞丅 戞擇偺栤戣偼丄惌嶔寛掕幰偑偡偱偵摿掕偺寢榑(尰忬堐帩)傪桳偟偰偍傝丄忣曬晹偑傕偨傜偡昡壙撪梕傪曄峏偝偣傞傛偆摦偄偨偙偲偱偁傞丅忣曬晹偺昡壙傪柍帇偟偨偺偱偼帺暘偨偪偺愑擟傗惌嶔崻嫆偑媈傢傟傞偺偱丄忣曬晹偺寢榑傪婯掕偺曽恓傗惌嶔偵増偆撪梕偵側傞傛偆丄奺庬偺埑椡(梊嶼偲恖帠)傪壛偊傞丅偙偆偟偨尰徾偼丄僀儔僋奐愴偵摜傒愗偭偨暷崙僽僢僔儏惌尃傗丄價僨僆傪旈枾丒旕岞奐偲偟偨愬扟姱朳挿姱偵傕傒傜傟偨丅 丂戞嶰偺栤戣偼丄愭擖娤偵偲傜傢傟丄傾儖僛儞僠儞偑抜奒揑偵峴摦傪嫮壔偟丄偦偺堄恾傪寈崘偡傞偼偢偲偺慜採偐傜敳偗偒傟側偐偭偨丅嫼埿偺昡壙偵偁偨偭偰丄孯帠娭學幰偼憡庤偺擻椡傪拞怱偵昡壙偡傞偑丄惌帯娭學幰偼擻椡傛傝堄恾偵拲栚偟丄幏漍偵憡庤僩僢僾偺堄恾夝柧傪廳帇偡傞丅層嬔煼庡惾偵戝朘拞抍傪憲傝崬傒丄愴棯揑屳宐傪嫮挷偟偰偒偨柉庡搣惌尃偼丄婋婡娗棟偺尨懃偑乽庡娤傪攔偟嵟埆帠懺傪梊憐偣傛乿偲偄偆偙偲傪妛傫偱偄側偐偭偨傛偆偩丅 |
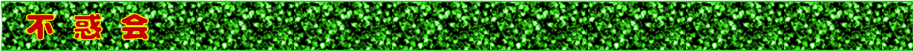
嘊