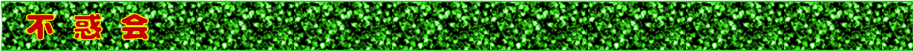
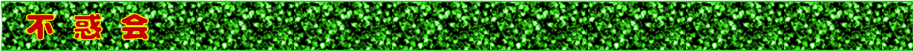
④
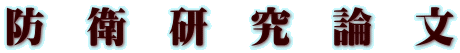
| 4 対米期待―米国は英国の要望に応えたか? (1) 米国のジレンマ 「アルゼンチン軍のフォ島侵攻か」という緊迫情勢の3月30日、米国は「いずれの側に立つか」について、ジレンマに陥っていた。米州機構加盟国との間には『リオ条約』に基づく集団安保があり、アルゼンチンは中南米諸国への地上軍派遣・共産ゲリラ掃討について米国の要請を受け入れる優等生だった。他方、英国に対してはNATO条約による支援義務が存在し、これを無視すれば欧州全体との関係がぎくしゃくする。とくに英国は、核戦力の強化を図るべく米国のトライデントの購入を勧めており、巡航ミサイルの英国配備交渉も大詰めを迎え、サッチャー政権は内外の反対を押し切って米国案を受入れようとしていた。 こうしたことから米国務省内では、カークパトリック国連大使が「英国に肩入れしすぎて南米諸国との関係を損ってはならない」と持論を展開し、「英国との特殊な関係」を優先するヘイグ国務長官(NATO司令官としての経歴を持つ)と対立していた。レーガン大統領自身は、サッチャーの対ソ核戦略に関するこれまでの支援に感謝していたが、この問題に関しては中立を貫く決断を下した。 第三国間の領土紛争に対する米国の対応は、国益と自国が持つ利害関係、その中での当事国間の領土問題の次元、他国への影響の程度や国際秩序の維持を考慮したうえで、「善意の第三者」に止まらざるを得ないという立場を原則としている。3月31日午後、レーガンはガルチェリに対し、「外交決着のお手伝いをする」として作戦中止を説得した。だが、「米国に貸しがある」と考えるガルチェリは聞く耳を持たず、「最終的に米国はアルゼンチン支援に廻る」と確信していた。一方、レーガンの電話を受けたサッチャーは、侵略を仕掛けたアルゼンチンと同列に扱われることを嫌っていた。そこでレーガンに対し、英国寄りの仲介を強く求める公電を届けた。 (2)英国の引き込み vs 米国の巻き込まれ 4月2日、奇襲侵攻に成功したアルゼンチンはフォ島で占領統治を開始し、英国は機動部隊の派遣と奪回作戦の準備を始めた。この間ヘイグは、ロンドンとブエノスアイレスを二度づつ訪問し、調停にあたった。だがサッチャーは、「挑発しないのになされた侵略には抵抗すべしという原則こそ、今後の国際秩序にとって最も重要であり、米国はいつまでも中立的態度にこだわるべきではない」と、調停案を突き放した。ガルチェリに対してヘイグは、「英国は奪回作戦を真剣に考えている。そうなれば米国は英国を支持せざるを得ない」と、脅しを交えて説得に当たった。しかしガルチェリは、「英国が機動艦隊を派遣しても、アルゼンチンの制海・制空権の優位は変わらない」との見通しの下で、米国に経済制裁の中止と、英国に艦隊の航行停止を働きかけるよう求め、ヘイグを「英国の代理人」だと激しく非難したのである。 アルゼンチンの占領で防衛態勢の強化が進むことから、サッチャーは機動部隊の出港や奪回構想の具体化に伴い、米国の中立姿勢に苛立ちを見せた。そして、核戦略問題で米国に妥協したことや、イランにおける米国大使館人質事件(1979年)での支援で「貸がある」と主張し、英国支持を鮮明にするようヘイグに迫った。軍事面でも、ヘイグと旧知のルーイン参謀総長を差し向け、直接支援を強く要請している。13,000kmに及ぶ遠征作戦と、奇襲を受けたことによる兵站準備の不足から、米軍の協力は欠かせない。そこで、ブラジル・ウルグァイ・チリ等の南米諸国に基地借用を打診する一方で、NATO加盟国にも協力を要請して米国に側面から圧力をかけさせた。 (3)英国の依存 vs 米国のアメとムチ ヘイグの調停が不調に終わった4月下旬、米国務省では再び「いずれの側に立つか」の議論が沸騰した。しかしサッチャー首相が、自国将兵の血を持っても領土を奪回すると宣言し、大規模の機動部隊を出港させたことから、米国世論は「国際秩序の維持」という原則を踏まえ、英国支援に傾き始めた。米国民は、正義と自助に敏感に反応する。そこで4月30日、レーガンは「武力侵略は断じて成功に終わらせてはならない。今後は英国に軍事支援を与え、アルゼンチンに経済制裁を加える」と声明した。 この演説を契機に、外交も軍事も流れは大きく英国側に傾いた。英軍機動部隊は、英本土とフォークランドの中間にあるアセッション島の米軍基地使用が許可され、米軍による間接支援が始まった。しかし米国は、基地や補給品を提供する見返りに、英軍の作戦に干渉した。戦闘をフォ島周辺の局地にとどめ、アルゼンチン本土への爆撃を認めず、早期に軍事決着を図らせようとした。英軍の上陸・奪回作戦を支援するため、人工衛星を用いた現地情報を継続して提供し、これが奪回作戦の促進に決定的役割を果たした。一方、アルゼンチンに対しては、英軍による本土爆撃がないことを保証し、停戦後の英国との政治交渉において仲介する (有利に働きかける) ことを約束していた。 (4)英国の不満 vs 米国のグローバル戦略 6月中旬、英国の奪回作戦が成功して戦闘が終結した直後、米国は中南米諸国が国連に提唱した「英国とアルゼンチンのフォ諸島の将来に関する交渉再開」決議を迷わず支持し、中南米諸国との関係修復を急いだ。もちろん軍事決着がついたと見る英国はこれに猛反対したため、ロンドンとワシントン間で新たな衝突が持ち上がった。また米国政府内では、「対ソ核戦略~欧州重視」を優先するヘイグ国務長官が、調停失敗の責任を取らされる形で辞任に追い込まれ、翌年には中南米政略の一環として『グレナダ侵攻』が行われた。 領土紛争に関する米国の戦争と平和の原則は、紛争が暴走して全世界の平和と超大国固有の利益を脅かしてはならないということにある。そのため、初期段階では中立的立場から調停にあたり、それが失敗した段階で紛争当事者の疲弊や軍事決着の一段落を見極めて和平の強制に乗り出し、その間他の超大国が庇護している国に不用意な介入はしない。なお英国は、この時の「借り」を忘れず、湾岸戦争・イラク戦争・アフガン派兵で米国の要望を入れて派兵に応じることで、「借りを返した」とされる。「米国のポチ」と揶揄されることもあるが、そうした貸し借りが米英の「特殊な関係」の一部をなしている。 二国間同盟にあっては、大国と小国の間に「保護」と「依存」という一面と、「統制」と「反発」という一面がある。それを端的に表したのが、鳩山政権の普天間移設問題での迷走(巻き込まれる恐怖)であり、菅政権の中国漁船体当たりに伴う安保条約5条の適用に関する米国への確認(捨てられる恐怖)である。しかし日本は、日米同盟の根幹である抑止力をないがしろにしてはならない。短期的には島嶼防衛と北朝鮮の核・ミサイル対応、中期的には中国の海洋進出、長期的にはロシアの脅威があり、米国との同盟の必要性は英国の比でない。効果的な多国間の安全保障体制が存在せず、多くの潜在的発火点を抱え、仲間のいないこの地域で、米国との同盟は貴重な安定化要因であることをしっかり認識しておく必要がある。 その一方で日本は、米国のアジア戦略が中国との衝突回避であることを、念頭に入れておくべきである。南シナ海での領有権争いで米国は、不介入を強調したし、東アジア域内の安全保障が「米国と中国の責任」だとも発言している。それらが、米中戦略対話を意識しての「ぶれ」であることも、承知しておく必要がある。フォークランド紛争においては、国連も調停能力・強制能力を発揮できず、加盟国・小国の失望を買った。領土紛争・防衛に関する限り、自助努力が原則であり基本である。 |