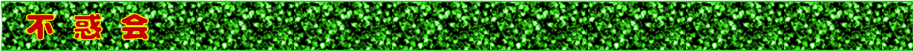
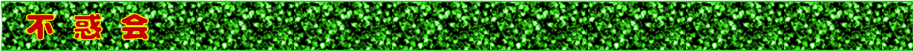
「事に臨んでは危険を顧みず」精神の涵養 上
空挺団勤務の回顧から

| 目次 1 隊付勤務―命を賭ける集団の臭い 2 基本降下―「技」の習得と連帯感 3 勤務と俸給―自衛官は職業に非ず 4 治安出動準備―自信過剰の錯覚 5 展示降下―名誉を賭けた広報 6 災害派遣―現場指揮官の責任 7 降下訓練事故―殉職隊員の処遇 (以下、下巻) 8 陸曹の人生観―即応と降下回数 9 落下傘の整備―連帯感・戦友愛 10 空挺団演習―現場主義と規則 11 空挺魂―自己顕示・忠誠の対象 12 精神障害―解決の難しい課題 はじめに 『偕行』1月号に掲載された岩田陸幕長の講話と、それに対する従前会員の質問と回答に目を引かれた。 質問は、「民主主義教育を受け、人権・人命尊重意識の強い今の隊員は、有事に本当に戦いうるのか? 戦争(実戦)体験がないが、精神教育は大丈夫か?」というもので、自衛隊ОBの一人として「おやおや、失礼な質問だな」と思った。 すかさず陸幕長は、「一言で御返事します。ご安心ください」と回答し、大震災での部隊・隊員の対応を引き合いに、「事に臨んでは危険を顧みず・・・」の宣誓通り、確実に任務を遂行するよう指示しましたと、きっぱり答えられた。 有事や戦いになれば、平時に培われた「規律・団結・士気」の他に、忠誠心・戦友愛・自己犠牲・部隊の名誉・戦死者の扱い等が求められる。 指揮官経験のない従前会員や、自衛隊経験のない大先輩の方々には、そういう精神要素を自衛隊員はいかにして育んでいるのか、身につけているかに関して、疑念や不安があるのだろう。 たしかに、各種の災害派遣や各国のPKОで任務を果し、無事帰国した隊員諸君が口にする言葉は「準備訓練の周到さ」「日頃の訓練のお蔭」という決まり文言である。 そうした物言わぬ・自慢せぬことを誇りとする自衛官の言動からは、大先輩の方々が持つ疑念―自衛隊は戦えるのか―を払拭することは難しいのかもしれない。 そこで、筆者の青年幹部時代を振り返り、といっても40年も前で、既に時代の流れを知った後知恵だが、自衛隊における軍人精神等の涵養について紹介したいと思う。 但し、個人的体験・所見であり、空挺という特異な職域であり、現在の自衛隊・自衛官の姿や価値観ではない点を断っておく。 注 自衛隊法53条「服務の宣誓の義務」 「私は、・・・・自衛隊の使命を自覚し・・・強い責任感を持って専心職務の遂行にあたり、事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に努め、もって国民の負託にこたえることを誓います」 1 隊付勤務―命を賭ける集団の臭い 筆者は昭和18年生まれの70歳。小・中・高校を神戸で過ごし、37年に防衛大学校に入校した。 出身地の関係から海上自衛隊を希望したが、桑江良逢(55期)大隊指導官の勧めで陸上自衛隊に宗旨替え。41年に卒業し、幹部候補生学校で一年間鍛えられ、普通科を選び空挺団を希望し、1966年に任官した。 60年代の日本は、高度経済成長が始まっていたが、自衛隊に対する国民の目はまだまだ厳しかった。 中学時代に60年安保騒動を発売されたテレビで見て驚き、70年安保闘争を予期しつつ防大を卒業した。 同期生でも浪人組には、60年安保でゲバ棒を握った経験者が何人かいたが、彼らが積極的に体験を語ることはなかった。 この時、空挺団を原隊として志願した同期生は、約400名中の11名(B9・U2、職種は普・特・施・通・需)で、習志野で初級幹部としての一歩、隊付を始めた。 普通、転入者は所属長かトップに申告した後、職場に案内されて紹介される。 ところが空挺団では、まず体力・胆力テストから始まり、教育係の先輩幹部が花見侃(47期)空挺団長に「11名、合格しました」と報告した後、団長への申告が行われることになっていた。
我々は赴任直前、教育係の先輩幹部から「手荒い歓迎式があるので、覚悟して赴任せよ」と連絡を受けていた。 全員が揃って正門を入り、直ちに半長靴・戦闘服に着替え、先輩幹部に続いてレンジャー障害路を3周し、降下用の跳び出し塔から跳び下りるとの予告である。 そうしたテストは、新品3尉に対する空挺幹部団伝統の歓迎(?)行事だった。 申告の場所は隊内クラブ。全幹部が集まる中、汗と泥にまみれたまま、11名が団長に申告。 続いて、大杯になみなみと注がれた清酒の一気飲み。その後自己紹介。 更に、代表者による切腹の作法(将校としての責任の取り方を知らしめる)の展示と、行事は続いた。 どんな訓示を受けたか覚えてないが、一連の行事は若手幹部が切磋琢磨する「不立(ふりゅう)会」への入会審査だった。 時代がかっていると思ったが、プロの世界とはこんなものかと驚きつつ、「この先どうなるか」と心配したことは言うまでもない。 当時の空挺団には、陸軍関係者がたくさんおられた。 後の倉重翼団長、小林正信団長、田中賢一副団長、田茂佐一・柏木明普通科群長、本間睦夫教育隊長等である。 隊付幹部にとっては「雲の上の人」だったし、戦争体験談とか軍人はかくあるべし論は記憶にない。とは言ったものの、本間一佐には厚かましくも後に結婚の仲人をお願いした。 プロとしての精神論や知識論は、教育係の先輩幹部に任されていた。 場所は、隊内の隅にあるBОQ(独身宿舎)で、時間は課業外。木造一階建ての大部屋、真ん中に石炭ストーブがあり、二段ベッド。 小さな机が一つあるだけ。テレビはまだなく、ニュースは中隊娯楽室まで出かけて見た。 隣室は、独身の先輩幹部が数名おられ、隊内飲酒もひそかに(?)やっていた (買い出しは我々、カネは先輩もち) 。 夜のBОQは、政治に対する悲憤慷慨の場、理論武装の場だった。 憲法の早期改正、自衛隊の国軍化、国民の国防義務、共産主義理論の欠陥等が叩き込まれ、防大・幹候の評論家的思考(?)から自衛官の理論に切り替える洗脳(?)教育であ.る。 こうした隊内生活が、後に「三島事件」と空挺若手幹部の関係を疑われるきっかけとなったのだろう。 だが未熟な我々は、高尚な理論を受け入れ咀嚼する心理・時間・能力を持ち合わせていなかった。 隊付期間中は空挺訓練が許されてない。 空挺マークのない新品3尉の職務と言えば、当直幹部であり、警衛司令である。空挺降下で中隊隊員が出払う場合は、「ちょうどいい」ということで特別勤務を命ぜられた。 余禄はタダ飯を食えることだが、陸曹・陸士と直接接して本音が聞けるという大きなメリットがあった。 その機会を通じ、先輩幹部の説く空挺隊員としての建前と現実には乖離があり、彼らにも人間らしさや弱さがあることを知った。 一方で、対外巡察や警衛司令を通じ、飲酒による帰隊遅延、チンピラとの喧嘩処理で隊員から感謝された。 当時の空挺隊員は、ケンかと聞けばすぐ助っ人として集まったので、負けるのはチンピラ側。警察へ身請けに行っても彼らは、「お騒がせしました」どころか意気揚々としていた。単純なる戦友愛を実感させられたものである。 今から思えば、隊付・ルーキーイヤーは槇イズム「良き社会人たれ」をしばらくおいて、もう一つの槇イズム「腕に力は抜けていないか、心に遅れはとっていないか」を実践する期間だった。 プロ野球・相撲のルーキーは「心・技・体」の充実が求められるが、「技」の修練を封じられていた隊付中の我々は、常に曹士の先頭に立つという気力と体力の錬成―恰好を付けること―を教わった。 「事に臨んでは危険を顧みず・・・」について言えば、その臭いをかぐことで、これから何をすべきかについて知り得た期間だった。 2 基本降下―「技」の習得と連帯感 「藍より青き、大空に大空に・・・見よ落下傘、空を征く・・・」。 「空の神兵」にあこがれて空挺を志願する隊員は、現代も後を絶たない。 当時の降下訓練は「東京タワーの高さから、新幹線のスビードを振り切って跳び出す」と説明された。 東京タワーができ、新幹線が開通し、東京オリンピックが終わり、高度経済成長が始まっていた。 降下そのものは、幹部だろうが陸士だろうが、一定レベルの練度が必要で、危険の程度は階級に関係ない。 そのため、すべての訓練生に同一内容と練度が要求される。
約3週間の地上訓練と、5回の実降下を無事終了した者に空挺マークが与えられる。 だから、高齢の幹部志願者にとっては体力的にかなりきついし、若年の陸士・陸曹・幹部にとっては初めて「命を賭ける・預ける」という心理状態に直面する。 指導にはベテランの教官・助教があたり、訓練施設・内容は米軍システムを採用している。 旧陸海軍も落下傘兵の訓練や空挺作戦を遂行したが、そのシステムは採ってない。 地上訓練の細部は省くが、要は同一手順を全員に完璧に体に覚え込ませるよう繰り返すことである。 共通したチェックの手順と点検行動を、階級を問わず採らせることで、降下者全員の安全を常に確認・確保し、地上戦闘に結びつけるわけだ。 地上訓練を終えるといよいよ初降下。 教官・助教を含め、誰もが緊張する。前夜、教官は学生に対し「両親・家族・原隊に手紙を書いておけ」と言い渡す。 気分だけは出撃前夜の特攻隊員で、遺書をしたためよと言うが強制はしない。 隊舎にある1個の公衆電話に長い列ができる。 それを終えると学生達は、空挺靴の手入れ・戦闘服のアイロン掛け。ロッカーの整理も怠らない。 さすがにクラブに行って飲酒する猛者はいない。 彼らは、訓練練度に自信を持っているが(教官・助教は暗示をかけている)、前の晩になると「飛行機から跳び出せるか・・・落下傘が開くか・・・」との不安が一気に高まる。
降下当日、教官・助教も機上で指導し降下するので、手入れの行き届いた下着や戦闘服を用いる。 筆者も降下日には褌を着用し、万一の際の足の骨折や手術に備えていた。 天候予報と風向風力がチェックされ、GОとなればトラック(後に、精神的負担を軽減するためバスが導入)で飛行場に向かう。 車中ほとんどの学生は、黙っている。居眠りする者は、昨夜緊張で寝つけなかった者たちだ。 飛行場に着き、大・小便を済ませる。滑走路周辺に便所はないし、搭乗すれば後は・・・・。 その後、待機中の輸送機と対面。もう後戻りできないと学生たちは覚悟を決める。 次に、各自が落下傘の交付を受ける。 積まれた中から開傘する傘を選んだかどうかは、自分の運にかかっている。選んだ傘を信用するしかない。 搭乗30分前、落下傘の装着と点検を自己の責任で行う。 背後の落下傘の点検確認は、次の降下者が責任を負うというのが空挺特有のルールである。 中隊長・小隊長に続く降下者は通信手・伝令が普通だから、彼ら一士・士長と言えども真剣になる。 それが、「戦友愛」や「信頼感」につながるので、空挺降下間は階級より経験がものをいう。 双発プロペラのC46輸送機に、よたよたしながら搭乗し、折り畳みキャンバスの席につく。 エンジン始動で機体が揺れ、着陸のない片道切符であることを反省してももう遅しとなる。 機内では、教官・助教が学生の顔色を窺っている。 真っ青な者は恐怖感に捉われており、真っ赤な者は緊張・興奮している。 旅客機と異なり、雲の下・中を飛行するので風や天候で機体が乱高下する。漏らす者、ヘドを吐く者も出てくる。 演習場に到着。試験降下員が飛び出す。地上から「風は良し、降下OK」の合図が来る。 いよいよ学生の初降下。1回目は連続ではなく単独で降下。 教官の合図で跳び出し口に立つ。誰もが風圧の強さに驚く。何せ新幹線の早さである。 尻を叩く合図で跳び出すはずだが、・・・実際は風圧に負けて機外後方に飛ばされている。 無我夢中で自然の法則に従うのみ。降下カウントを忘れ、ドンと開傘ショックに見舞われる。この間わずか4秒。 空中に浮いている間に地上の集合点(赤旗)を探さねばならないが、どんどん地上がせりあがってくる。 身体が風に流されている、と思う間もなく着地、回転。無意識のうちに訓練どおりの手順ができる。 着いたと安堵する間もなく、傘を外さねば風に引っ張られる…。 教わった通りに傘を背負い、よたよたと集合点に向かうが、わからない。 地上にいる助教が「オー、やったな・・・」と笑顔で迎え、「あっちだ」と集合点を指し示す。 学生が「やった」と感じるのは、傘を担いで集まる途中だ。 風圧に負けてズッコケたことも、予備傘を用いるカウントを忘れたことも、傘を操作して目標に接近することも記憶にない。 力の限りと言うが、無意識にそれに近いことができたわけだ。 2回目は連続での降下。3回目は、武器携行降下。4回目は、武器と装具携行。 そして最後は戦闘降下で、着地後に簡単な戦闘行動が課せられている。 その後、隊列を組んで駐屯地に凱旋する。 その日は、団長をはじめとする空挺隊員が営門から並んで出迎え、新米空挺隊員の誕生を祝う。 5週間の訓練を無事に終え晴れて空挺隊員として認められた学生たちは、階級を超え汗と泥と涙と感動にひたるのである。 空挺マークは、単なる技能取得の証だけでなく、生れて初めて命運を賭けることを自ら選び、それに耐え抜いた男たちにとって人生の勲章であり、本物の兵士としての証でもある。 だからそれを讃え、仲間として歓迎し、相互に信頼する。 空挺隊員の団結が強いのは、そうした訓練に共に耐えてきたという「特別の連帯感」が根底にある。
3 勤務と俸給―自衛官は職業に非ず 胸に空挺マークが有るか無いかで、駐屯地の生活様式は大きく異なる。 空挺団所属の隊員になれば、手当が付く。階級初号俸の33%だから、新品の2・3尉でも5〜6千円になった。 俸給4万5千円程度の時代だから、大きかったと思う。さらに、一回の降下毎に3千円の手当が付いた。 但しこれは月2回まで、それ以上は支払われない。 高度成長・俸給・諸手当の見直しに伴い、降下手当も次第にアップしたが、なぜか宴会代1回分の額にスライドしており、現在は6千円程度と聞いている。 たしかに降下を終えた隊員は、緊張感からの解放、無事降下の祝杯、安全確保の自慢とかで、よく飲んだ。 習志野駐屯地の隊内クラブの売り上げは全国一だと、まことしやかに喧伝されていた。 空挺隊員手当や降下手当は確かにもらった。が、「残ったか、役に立ったか、貯金したか」と問われれば、何も残らなかった。 唯一、制服だけは官品の補給物品を用いず、特別誂てカッコよさを競った(同僚は裏地を赤にして粋がっていた)。 もう一つは、第一種礼装と儀礼刀を新調した。 同期の結婚式で、新郎・新婦を剣のアーチで祝福しようと約束していた。 それ以外は、今日の緊張と疲労を取り除き、明日の降下や任務に精を出す糧として駐屯地周辺や、船橋の歓楽街を同期で飲み・食い歩いた。 中古の車を買った先輩がいたので、それで船橋までぶっ飛ばした。飲酒運転の取り締まりが緩かった時代である。 それらは、青年幹部の通過儀礼だったと言えよう。単純明快な男同士の世界に酔っていた。 高度経済成長、列島改造ブームの情勢で、2等陸士の募集は極めて難しかった。 そこで防衛庁は、自衛隊は各種―自動車運転・車両整備・特殊車両免許・高圧ガス取扱い等―の技術・資格・免許が取得できる「職業」だと宣伝し、ダイレクトメールや縁故募集作戦を開始した。 他の職業との差別化をアピールしたのである。 しかし空挺の若手幹部団は、自衛官の勤務を「職業」とする考えに強く反発していた。 自衛官の勤務は、後に「3K」と言われるように「きつい、きたない、危険」そのものであり、それを克服して耐え抜くことに意義や意味があると考えていた。 戦闘に耐える軍隊、「使い者」になる軍事組織とは、結局のところ忍耐力のある人間集団だと考えていた。 定期的に食事が給与されなくても、あるものだけで我慢する習慣。 睡眠が足りなくとも、耐えて本隊のために見張りをする。寒さや雨にめげず、重い装具を負って1日に12時間以上も歩き続ける。 周辺に友軍がいない場所に潜伏し、敵情を報告し続ける。こうした行動は、すべてに忍耐力が要求される。 それらを克服して一人前の戦士になった部下を率い、国防の末端に参画することに喜びを感じる一方で、その手段として給与・手当が与えられていると考えていた。 しかし一般的な職業観は、自分の自由時間、能力を切り売りするものであって、全知全能を預けるものではなかった。 ペイに見合うだけの能力を提供し、いやになれば職業選択の自由・休職・転職が奨励される世の中へと変わりつつあった。 空挺隊員に支給される隊員手当の意味は、空挺勤務の即応態勢に見合うペイだとは誰も考えてなかった。 事実、サラ金業者から行方をくらますために空挺を志願する者はいたが、サラ金の穴埋めに空挺手当をあてにしている者はいなかった。 4 治安出動準備―自信過剰の錯覚 当時は、70年安保闘争が予想され、治安出動訓練が連日行われていた。 精神教育では、東大・安田講堂への侵入を企図する暴徒と、これを阻止せんと放水する警察官の映像が繰り返し放映され、各地で行われる陸自部隊の訓練映像も見た。 隊員が暴徒の役割を担い、真剣に角棒で隊員に襲い掛かり、催涙ガスも用いられていた。 その結果、他部隊に対する競争心が芽生え、全学連や革マルに対する敵愾心が高揚した。 一般国民と暴徒を区別して考えたが、「殺すとか、殺される」との意識はなかった。 但し、騒乱を鎮圧せよという命令があった場合、どんな手段をとって命令を実行するかは出動部隊指揮官の判断にゆだねるべきと考えていた。特に、威嚇を含む銃の使用についてである。 空挺団は、大型ヘリによるVIP救出という任務を担任した。 官邸やNHK放送局は地上からの接近が暴徒に阻止され、屋上は電波アンテナ等で着陸不能と考えていた。 そこで、対象とする建物の模型や見取図を作り、幹部は暗記するまで覚え込んだ。 そして連日にわたり、実機を用いたリぺリング・飛び降り訓練に明け暮れた。 小・中隊レベルの装備は、小銃の携行が許されず、ガスマスクと盾と長木銃を携行した。 若手幹部は、小楯(便所の蓋と軽蔑した)を持つ姿は機動隊と同じで、軍隊らしくないと不満を漏らしていた。 筆者も3尉の小隊長として、降下・制圧・要人救出訓練の先頭にあたったが、大型の盾がヘリの風圧に巻き上げられ、騒音と埃の中で負傷者がかなり出た。 70年6月が近づくと、複数のヘリが駐屯地に常駐し、上級幹部も駐屯地に寝泊まりし、大量の蛇腹鉄条網・スリングロープ・大盾が車両に積み込まれ、待機態勢に入った。 新品3尉の小隊長としては、与えられた任務を坦々と遂行する責任感から、迷いや躊躇は一切なかった。 悲壮感もなく、双方にけが人が出ることもやむなしと考えていた。 現場でのVIP捜索・救出、不側事態への対応が求められる小隊長としては、火急の場合に「ついてこい」と命じ得る陸曹を選んでおくことが欠かせない。 その時に備え「俺が行く」という複数の陸曹と、「あいつなら大丈夫」という小隊の雰囲気を醸成しておく必要があった。 それをヘリの騒音の中で、アイコンタクトと手信号で指揮することが求められていた。 そのためには、普段からこちらの気ごころを伝えておく必要がある。 飲みにケーションでカネも時間も使ったが、小隊の陸曹もまた「士は己を知る者のために働く」のである。 何のことはない、防大運動部時代における後輩掌握術の延長だと、なめて考えていた。 末端の小部隊における戦闘遂行の能力は、小隊長と隊員との相互作用の中で生成され、正当化されて勢いづく。 しかし他方でその能力は、小隊長の個人的認識や主観・偏見に大きく左右される危険がある。 今から考えると、空挺団時代の小隊長職は、「力が絶対」とする偏見の下で、「自信過剰」という錯覚に捉われ、「俺が責任をとる」という幻想に見舞われていた。 錯覚の側面には、実力以上に体力でパフォーマンスを増幅させ、空挺=精強と言うスローガンで陶酔感を煽り、全体や弱みを見なくなっていた。 今から思えば、当時の通信・兵站・装備は貧弱であり、己の能力も未熟(特に防衛法制や警察官職務執行法)で視野が狭く、熱気に包まれて勇んでいた。 あの時、出動が下令されずよかったと反省し、幸運に感謝している。 5 展示降下―名誉を賭けた広報 2等陸尉になる前、降下訓練・レンジャー等の教育隊教官に転勤した。 その頃のマスコミは空挺団について「クーデターを起こす部隊」ではないかとの疑念を抱いていた。 後進国のクーデターには空挺部隊が絡んでいた。三島由紀夫の割腹事件が生起する前である。 マスコミの空挺団に対する見学・取材申し込みは多かった。 上級部隊は、訓練取材はОKだが隊員へのインタビューは断る方針をとっていた。 今のように、「訓練を見せて抑止力につなげる」「国民の理解と協力を得る」との発想や広報戦略はなかった。 だから空挺団本部は、取材協力に一般隊員を含めず、空挺訓練生に限定した。 教官としては「なんだ又か・・・」と言うほど取材協力が多かった。 取材側も、珍しいもの、危険なもの、恐ろしそうなものを撮る傾向が強かった。 だから、「やらせ」を求められた現場では、訓練の阻害事項、訓練生の気が散る、危険につながると見て、取材への協力を嫌がった。 変わったもの、珍しいものをテレビで見せる企画のはしりの時代で、そのうちレンジャー訓練や蛇を食する方向に向かったが、自衛隊の本質「事に臨んでは身の危険を顧みず・・・」に迫っていたとは思えない。 恐ろしいもの見たさの好奇心を満すだけで、国民と自衛隊との距離は詰らなかった。 むしろ、ボーイスカウトに対するロープ訓練や生存訓練は大変喜ばれたし、支援した隊員たちも人生意気に感じていた。 広報で厄介というか、危ないのは展示降下だった。 全国各地で○○基地開設記念等で「ぜひ空挺降下を行ってくれ」と言う依頼は多い。 「お座敷がかかった」として、地元出身隊員を中心に人選が行われる。 親兄弟・同級生・友人に晴れの姿を披露できる―故郷に錦を飾る―機会である。 だが、遠慮する者も多かった。と言うのは、行事に防衛庁長官(当時)や国会議員が招かれる場合、少々の横風・強風でも降下をしなければならない。 上官たる防衛庁長官に対し、「風が強くて危険です。できません」と直言するには、現場責任者として相当の勇気と覚悟がいる。 展示降下は少々の風でも「やらねばならない」のである。 筆者は、海自・下総飛行場での展示降下に参加したが、この時は死ぬかと思った。 訓練規定で風速8m以下と決まっているが、そこは心得た測定隊員が風の弱まった瞬間に計測し、「制限内です」と報告する。 機上では「横風が強いゾ」と注意は受けるが、とにかく無事に済ませたい。 降下場は滑走路で、横風が強ければ上空を旋回して風の収まりを見る。地上からは、長官の時間の都合があるのでもう待てないと降下を催促してくる。 機上では、先頭降下者以外、下界の状況は全く分からない。 降下開始の青ランプが点いてベルが鳴り、前の者が飛び出せば自動的に続いて跳び出す。 風が強いときは、傘の流される距離を計算し、降下場外=民有地上空に跳び出し点を設ける。 だから、跳び出した瞬間、「えーッ、降下場外!!」。「木にひっかかる!!」と悲鳴があがる。 傘を操作して何とか降下場・滑走路への着地をめざす。 一方で、空中操作を誤って基地外に着地する者が多数出る。小生は何とか滑走路に着地・叩きつけられた。 だが今度は、帆掛け船の如く落下傘に引っ張られて起き上がれない。腹這いのまま滑走路を引っ張られ、「これはだめだ。死ぬことはないが骨折か挫滅は免れまい・・・」と覚悟したものだ。 結局、予備傘と半長靴がコンクリートの滑走路との摩擦で擦り剥け、足指の挫滅程度で終わった。 滑走路の端にある外柵に傘がひっかかり、ようやく止まったのだ。 後で聞くと脳震盪を起こした者、梨園に張り巡らされた鋼線にひっかかった者、多数。アンビランスが駆けまわり、衛生隊員と落下傘回収員があたふたと救助にあたった。 翌日の新聞は、開設記念日の大臣等の祝辞は載せていたが、展示降下後のアクシデントは報じてなかった。 地方紙・地方版は政治家の圧力に弱い。 観客は、落下傘の華に満足していたが、「風が強くて着地が大変だ」ということはわからない。部隊の名誉をかけてスタントマンのごとき役割も果たさなければならない。 空挺部隊は、陽動作戦、緊急展開、捨て石作戦にも使われる。 作戦全体からみればそれらは必要不可欠なのだが、大損害が予定される部隊にとってはたまらない。 原則としてその場に遭遇した下級幹部は、率直に状況を曹士に説明し、彼らに理解させるのだが、実際にそれは極めて難しい。 運命としてあきらめるしかないと知りつつ、上級部隊等への不満や反発が爆発する。「事に臨んでは・・・」にもいろいろなケースがあるということだ。
6 災害派遣―現場指揮官の責任 1970〜80年代、左翼やマスコミは「特殊部隊」を危険なものと見ていた。 国民を対象にし国民に銃を向ける部隊、ベトナム戦争における秘密部隊だと警戒し、国会でもそうした問答が繰り返されていた。 一方で、相次ぐハイジャック事件から、警察庁と防衛庁はそれらに対応する特殊部隊・作戦の必要性に注目していた。 陸自の上層部は、特殊部隊を新編する場合は空挺団の一部を中核として編成する構想を練っていたようだ。 そこで、空挺教育隊の教官を米国本土や沖縄米陸軍に派遣し、特殊作戦・特殊戦技の取得・導入を先行的に行わせていた。 空挺教育隊に配置換えされた筆者も、その構想に則っていた。 江田島・海自の潜水課程に2か月(フロッグマンの養成)。松本連隊の山岳レンジャーに1か月。空挺のヘリ戦技集合教育に1か月。 沖縄のスペシャルフォースへの隊付きは実現しなかったが、学生教育の合間にいろいろな戦技を習得した。 成田空港が開港の運びとなった時、ハイジャック対応の担当を自衛隊にするか警察にするかで綱引きが行われ、結局、成田国際空港特別警備隊(警察)の発足が決まった。 防衛庁・自衛隊側の敗北である。末端に居る小生には、当然ながら、全く知らされなかった。 (注 現在の習志野駐屯地には、中央即応集団隷下の「特殊作戦群」が所在し、多くの空挺隊員が編成に組み込まれている。)
そんな夏のある日。那須空挺団長から呼び出しがかかった。 「おい、すまんが水難救助に行ってくれ。荒川だ。潜水器具を使える陸曹何人か連れて行け。ヘリが到着次第出発」。 この時は、子供の死体が上がったので、派遣中止となったが、水中で人を探す活動はやったことがない。 江田島の潜水課程は水中爆破の準備で、機雷等の捜索は船舶・レーダーで行う。 「どうやって探すか知恵を貸せ」と陸曹を集め、一応の成案を出していた。 作戦の検討段階でチャーチルは、幕僚長の討論の後に彼が判断を下す「討論による独裁」を好んだが、2等陸尉に自ら判断する知識も経験もない。 それらを陸曹の経験と知恵に頼り、責任は負うという、何とも頼りない作戦検討過程を経ての準備だった。 数日後。今度は山中湖でボートが転覆。 アベックが行方不明。再び団長の命令を受けてヘリで富士学校へ。引き続き車両で山中湖へ向かった。 当時の警察は、まだ潜水器具を持たず、レスキュー隊もなかった。行方不明から数時間たっていたが、生死は不明。 漁業組合が網を打って一応の捜索は終えていたが、藻のある水域は網を打てない。 そこを潜水具を持つ空挺団にお願いするという筋書きだ。 直ちに陸曹と水中捜索を開始。 現場付近は藻の繁殖地域で視界不良。また富士山の湧水箇所は極端に冷たい(後で聞いたが、死因は溺死でなく心臓麻痺)。 捜索方法は、三人にロープを持たせ、横一線で連携を保ちながら「生死不明の人を探す」。 水中ランプはあるが、それでも方向がわからなくなるし、藻に絡まる恐れもある。 なにより、気持ちが悪い・・・。(今から思うと、東日本大震災における隊員は、本当によくやったと思う) ボンベを取り換え約1時間後。水面に死体があがったと漁協から連絡。あとは警察の仕事。 感謝の言葉と段ボール2個分のトウモロコシをもらい、ヘリで帰隊した。 数日後、第3科から連絡があり、先般の山中湖派遣は災害派遣でなく、転地訓練として文書命令を出したとのこと。 人事ジャケットに記載されない結果となった。 災害派遣には、緊急性(生命に係る)、代替性(他に手段がない)、公益性(警察に協力)の原則がある。 死体捜索は警察の仕事で、事件とのかかわりを調べる活動だ。 生存していれば緊急性があるが、死体で上がれば緊急性はなかったと上級部隊は判断したのだ。 でももし部下が藻に絡まれて遭難した場合、訓練扱いでは不満が残る。 訓練となれば現場指揮官の責任が問われるし、弔慰金も少ない。遭難者の家族は納得しないだろう。 災害派遣で事故が発生した場合、それは「事に臨んで危険を顧みず」の結果であることは間違いない。 部下を預かる身としては「身の危険を顧みず・・・」扱いにしてもらいたいと、憤懣やるかたない状況で陸曹とやけ酒を飲んだものである。 この体験の数年前、武山の少年工科学校で渡河訓練中の生徒の水死事故があり、安全管理について上司がうるさくなっていた。 若手幹部たる我々は空挺志願者の能力を信頼していたので、防火用水を利用した渡河訓練を繰り返し、群長から大目玉を食っていた。 過度の安全管理は、現場指導者の訓練意欲を削ぎ、委縮させる。 また学生には、訓練は安全が確保されているとの誤解を与え、注意心や緊張感が削がれる。 したがって、訓練はどうしても甘くなり、実態よりペーパーと修飾語で評価される結果になりがちだ。 しかし災害派遣となると、国民の命や財産がかかっている。 また、救助・捜索活動に定型はなく、その場その場で現場指揮官が判断しなければならないし、自治体関係者・警察・消防もいる。 部隊の名誉にかけて、何とかしなければという「男気」が働く。 これが「事に臨んでは身の危険を顧みず・・・」の原動力になる。 警察も、消防も、危険な事態になると「自衛隊さんお願いします」と責任を転嫁してくる。 周囲の目も、「自衛隊なら何とかする」と期待する。 二次災害を出さぬため、代替え案を提示して引き下がるのもまた勇気がいる。 下級幹部であっても現場指揮官となれば、隊員の殺生与奪について権限を行使する局面にいやでも立たされ、責任を負いきれなくなるのだが・・・。 つづく
|
||||||||||||||||||||||||||
喜田 邦彦
6区隊 職種:普通科